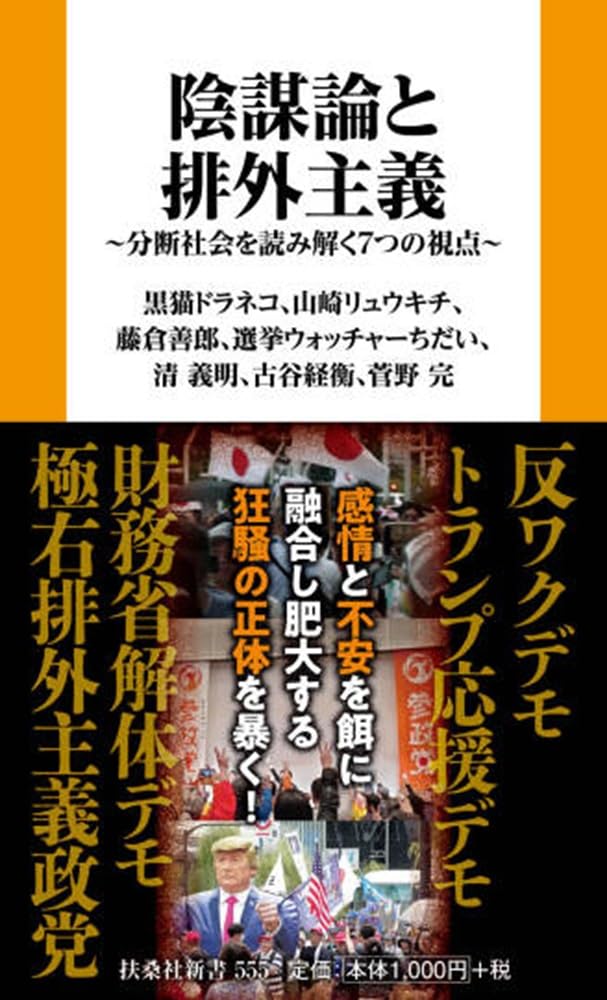Dec 31, 2025
年末の御挨拶に代えて本を紹介する
Dec 31, 2023
世界に平和を
ブログのトップに旗を貼った。
日本国内もひどいが、世界もひどい。
何ができるかと言っても、個人にできることは少ない。
でも、本当は、連帯すべきなのだ。
個人主義の時代というけど、イコール他人の不幸は気にしないという意味ではない。
痛みは連鎖する。
そして、皆を不幸にする。
他人の不幸に、自分のことのように怒るのは、むしろ当たり前で、自然なことなのだ。
当たり前のことが、当たり前な世界になればいい。
みなさま、よい新年を。
Dec 26, 2023
「プロフェッショナル 仕事の流儀 ジブリと宮崎駿の2399日」を観た(27日、追記)
2024.03.20. 追記。
ジブリ公式では「大伯父」とされたが、このサイトではずっと「大叔父」の表記が残っていた。
このたび「大伯父」に統一、修正した。
NHKがドキュメントを放送した。
宮﨑駿『君たちはどう生きるか』は高畑勲からの解放だった 『プロフェッショナル』を観て
https://realsound.jp/movie/2023/12/post-1523016.html
まあ、なんというか、驚いた。
あそこまで高畑への思いが強いとは。
たぶん、駿にとって父親のような存在だったのだろう。
ネット上には、そんな駿の姿を受け入れにくくて、恣意的な編集があるのではないかという見方も上がっているが、僕みたいなのが言うのもなんだが、写ってる画面自体の説得力がはんぱなくて、そんな見方は捻じ伏せられていると思う。 恣意的な編集は、そんなことをする余地がある場合にできることではないだろうか。
そして、あの映画が、どういう経過で作られたかが分かった。
いろいろと、腑に落ちた。
どう腑に落ちたのかといわれると、説明しにくいが。
おそらく最初は、失われたものたちの本と君たちはどう生きるかをミックスしたような話だったのだろう。そこに幼いころの駿をモデルにして主人公に据えるような。
高畑をモデルに描きたいというのは、最初からあったのだろうか。
少なくとも、高畑に見せたいというのはあっただろう。それは、多かれ少なかれ昔から、駿の作品にはあっただろう。
それが、高畑が亡くなり、別の話になった。高畑をモデルにしたキャラクターがいたとしても、生きているときに見せたいものと、亡くなった高畑に向けてのものでは、まったく違うものになるだろう。
あの、木に竹を継いだようにも見える構造の不可解さは、駿のモチベーションのベクトルが大きく変わったことによるのだと思う。あの映画は高畑への追悼であり、同時に駿自身の内面、長年にわたってアニメーションを作ってきた過去に向けての追悼でもあるのだ。
あの映画には、生きていく若い駿が描かれている。
消えていく大伯父は老いて力を失っていく高畑であり、駿でもある。
どのキャラクターのモデルが誰で、というのは鈴木プロデューサーからかな?、公開当初からわずかながら出されていたと思う。
しかし、深い内実は今回の番組まで晒されてなかった。この映画、内実を晒してしまったら、その内実だけで作品が語られてしまうリスクが大きいような気がする。
下手な宣伝は打てない。
とってつけたような表面的で売れ線な宣伝を打ったら、作品に込められた監督の内面を傷付ける。泥を塗ることになる。追悼を売るのかということになる。
宣伝を打てなかったのは、あまりにもプライベートが反映された映画だったからだろう。
鈴木氏は、見る人が見たらわかると言っていたような記憶がある。
たぶん、実際、そういう映画なのだろう。
今回、あの番組で、あそこまで制作側の、駿の内実が晒されて、作品そのものへの評価や観客の理解はどうなるのか、とは思う。
プライベートな映画は、アングラ(僕の言い方だけど)だったらやりやすいのだ。
大規模な商業映画ではやりにくいはずだ。
まあ、やっちゃったわけだけど。ふつうじゃないわな。
真人に向かって自分の時に戻れと叫ぶ大伯父のシーンを繰り返しアフレコする場面で、ドキュメントは締め括られる。
なるほど、これはそういう映画なんだな、と。
あれが大伯父の本音ということだ。
プロフェッショナル 仕事の流儀 ジブリと宮崎駿の2399日
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2023132680SA000/index.html
とても面白く、興味深いドキュメントだった。
再放送しないそうだ。
見たければ現状、オンデマンドで見るしかない。
しかし金払ってみてもいいのではないかと思った。
駿は新しい作品を作るだろうか。個人的には、未来の話を見たい。
彼の作品は、昔の話が多い印象がある。
コナンは未来の話に感じられる。あれ以降は描いていない。
ナウシカは未来といえないこともないが、あまりに遠くかけ離れていて実感がない。On Your Markというのがあるようだけど、どういうつもりなのかよくわからない。実際、実験なのだろう。
未来は描きたくないんだろうか。というか、暗い未来しか描いていない気がする。
明るい気持ちになれる未来ものを、また見たいなあと勝手に思う。
あと、今回のドキュメントを見て気付いたことがある。
高畑はコナンに関わっている。調べてみたら、ラオ博士を演出している。
だから、たぶん、やはり、大伯父にはラオ博士が入っている。これは、だからどうなんだって話だけど。
27日、例によって追記だ。
思い至ったこと。
大伯父は、自ら望んで、あの下の世界を作ったんだろうか。
実は真人のように呼び込まれるように入りこみ、出られなくなったのではないか。
いや、実際のところ、望んで行ったのかどうかは大して問題ではないような気がするけど。
落ちてきた石との契約、と大伯父は言った。
石には悪意があると。
悪魔との契約、なのかな、圧倒的な力の差がある相手に魂を売り渡す。そのかわりに大伯父が手に入れたのが、あの世界だ。
そして、あの世界を維持すること、後継者を求めるのは、石の意向でもある、のかな。
これは平等な取り引きか。
入り込み出られなくなったのは、たぶん、ひみちゃんも、キリコさんも、そうなのだ。なつこさんも、そうなんだろう。
自らの意思でそこにいるとしても、望んで居るわけではないのではないか。
落ちてきた石は、SF的に解釈をしたら2001年宇宙の旅に出てきたモノリスのようなものだ。
そこに大伯父が捕まって、何かを作り始める。
更に、ひみちゃんやキリコさんも引っかかる。
石の意志はモノリス同様、判然としない。野蛮な星を文明化させるのが目的なのだろうか、しかしそれならなんで下の世界なんか作ってるのか。
石の意志は伺い知れない。
石は人を眺めて、何を思っているだろうか。
そして大伯父は自分が作った世界を見て、何を思うだろう。得意になり上機嫌なわけがない。上の世界とは比べるべくもない貧困さに、絶望するはずだ。美しいところは上の世界のコピーだ。醜いところも上の世界のコピーだ。
彼は契約で、あの世界を半生にわたって維持してきている。
たぶんあれは、石の力で、本来の寿命よりも長く生かされているのだ。
ならば、真人が世界の継承を断り、あの世界が壊れることは、大伯父にとっても解放なのだろう。
なんだか、突っ込んだらSFになってきた。
しかし、ジブリの面々に当てはめたら、なんだか切なく暗くなるような話だ。
やはり物語と製作の内実を結びつけるのは、ほどほどにするか、分けて考えたほうがいいのではないかと思う。
Sep 27, 2023
ジブリの「君たちはどう生きるか」レビュー総まとめ(なんとか収拾をつけんと試みる)
さて、過去のレビューはこちら。3つもある。
ジブリの「君たちはどう生きるか」を観て
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230818a.html
ジブリの「君たちはどう生きるか」2回目を観て(風立ちぬとアーヤと魔女もちょびっと)
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230914a.html
ジブリの「君たちはどう生きるか」を俺はどう楽しむか(レビューその3)
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230916a.html
上記の通り、過去に3本のレビューを書いているんだが、まだ、総論的なことを書いていない。
なんで分かりにくいのかとか、部分やエピソードをどう解釈するのかとか、ちまちま書いてきてるが、この映画は何なんだ、どうすんだ、というのは書いていないのだ。
だから、少しだけど書いておくことにした。
何かがないと座りが悪い。
しかし、これって、総論なんてものになっているのだろうか。心許ないが、まあ、これで最後だろう、さすがに。
まずはお断りしておく。
僕は、青サギが鈴木プロデューサーで、塔がジブリでとか、そういう解釈は全く興味がない。
というか、数億円以上の金かけて2時間のアニメ映画を作って、内容の中心がそれってことは、そもそも有り得ない。
いや、知らないよ?、駿がそういうつもりで作った可能性は否定しない。
しかし、そんなアニメ観て、誰が楽しいのか。
だから、うちでは、そういう感じじゃなくて、普通のレビューを書いている。
普通に観客として観たら、何が気になって、何が分からなくて、何を面白いと思ったのか、そういうことを書くレビューにしている。意図してそうしてるというより、そういうのしか書く気がしないからだ。
世間でそういうのが少ないように見えるのは、ネタバレにならないように注意してる人が多いからだと思う。
逆に言えば、青サギは誰かなんて、本質じゃないということだ。
しかし、
パーツに理屈を付けるのに汲々とする気持ちは、分からないではない。
なにしろ、君生きは、分かりにくい。
もともと駿のアニメは、分かりにくいのが多かった。
もののけ姫あたりからそうなった。それでも千千とかはストーリーを読めたけど、ハウルとか意味不明だと思った。
今回、さらに分かりにくくて、多分、わざとだ、というのは過去レビューに書いた通り。
そして、こんなに分かりにくいアニメだと、分かるところから手を付けて、とにかく落ち着きたい気持ちは分かる。
本質じゃないところでも齧っていったら何か出て来る。そうでもしないと、分からないままでは、観客としては、納まりが付かないのだ。
僕なんかはたぶん、暢気な方だ。
せっかちな人だったら、投げ捨ててるだろう。
でも、だからといって大伯父は駿だと言われたって、こっちは何にも、ひとかけらも、面白くないのだ。
あと、元ネタだという「失われたものたちの本」も読んでいない。
読んで比較したら、駿が追加したものが何かが分かると思うのだけど、そこまでする余裕はないし、僕にとっては本質的なことではない。
前書き終わり。
とりあえず、今迄のレビューで何を書いたかをまとめる。
ひとつめのレビューで述べたのは、
1)タイトルになった本の重要性(上の世界での在り様、下の世界での現れ方、真人の石について)
2)なつこさんと真人の関わり、他者との関わりがどう描かれているか
3)下の世界の崩壊が、静かな印象だったこと
ふたつめのレビューでは、
4)風立ちぬとの比較、関係
5)ひみちゃんとひさこさんと真人について(観客にとって分かりにくいことについて)
6)ひみちゃんが上の世界に帰るために真人と会う必要があったというアイデアと、大伯父の意図
みっつめのレビューでは、
7)時系列からの考察(関東大震災、富国強兵について)
8)ヴァルハラとの類似について(ワラワラとキリコさんについて)
9)ひみちゃんとひさこさんと真人について(母子関係についての駿の表現について)
ざっとこんな感じ。
上記のように、ある程度まとまってる項目もあれば、キーワードだけなので上には挙げなかったみたいなものもある。まあ、いろいろ考えたものだ。
こうして考えていることがどういうことかというと、
結局、「僕のための君生き」がどういうものなのか、自分の中での構築を試みている、ということだ。
落ちてきた訳わからん隕石を、自分に合わせて建物でかこって体裁整えるようなものかもしれない。
僕にとって、作品に触れ、理解するとはそういうことだ。
過去に触れた多くの作品の中には、内容を理解できず、世界観を構築しきれなかったものも少なくない。しかし、途中で投げ出したくなったり、訳が分からないと思うのを、自分のものになんとかして、ようやく、その人にとって意味を持つものになるのだと思う。
作品に触れることは、他者に触れることと同じだ。
なつこさんと真人も、お互い、相手が何者なのか分からない。
しかし彼らは、彼らが抱えた問題を、ああ見えて、あの場面でなんとかしたので、上の世界に笑って帰ることが出来たのだ。
いや、本当はあの世界に降りる前、真人を誘う青サギをひさこさんが矢で追い払った、あの夢(2人は同じ夢をたのだと、僕は思う)、あの時点で、進む方向は、彼ら二人の心のうちに、できていたかもしれない。つまり、母子として、守り守られる未来の関係が、夢として現れていたのだと思う。
ひさこさんは、若くして亡くなった。小さい真人は知っていても、母を失いながら成長した真人の痛みは知らない。
真人は、母のことを、どれだけ知っていただろう。母親の思いを知るには、まだ幼い。
運命の狭間で、伝えられなかった思いを伝え合うことが出来たら。なくしてしまった石のかけらのようなものでも、大事なものだったかもしれないのに。
彼らは、大伯父の世界で会うことができた。そして笑って、上の世界に戻れる。
下の世界は、困難を抱えた、あるいは現実には不可能な、そんな関係をつなぐ、一種、奇跡的な廻廊だ。
大伯父が石を積み、それを具現化させている。
真人自身が、下の世界でその恩恵を受けて、たぶん、その自覚もあるはずだ。
それでも真人は、下の世界を引き継ぐことを拒む。それは、大伯父が作った世界に救われたのではなく、母親が「上の世界で」与えてくれたものによって、今の自分自身があるという気持ちが強いからなのだろう。
君生きは、観客にとって、真人にとっての青サギのような意味不明な何者かだ。周りからは何を考えてるのか分からない心を閉ざした真人みたいなものだとも言えるかな。宣伝しないのはそういうことだ。あのポスターは伊達じゃない。
たぶん、駿は、そういう存在になるように君生きを作ったのだろう。
どう読み解けばいいのかは、君生きの中に描いてある。と、たぶん、駿は言うのではないか。
そういえば他の人のレビューだと、他者性は、青サギと真人の関係で語られることのほうが多いようだ。
僕の場合、なんだかそこには引っかからなかった。
過去の駿の作品で、他者はどう描かれていただろう。
僕は熱心なファンではないので、自信はないが、明確に「他者とどう向き合うか」を、テーマに据えた作品はなかったように思う。
ナウシカでは、風の谷とトルメキア、あるいはナウシカ自身とそれ以外の人といった、理解し得ない関係が多々描かれた。しかしそれらは、物語の流れの中で、中心的な命題とはならないまま過ぎ去った。
ラピュタでは、パズーとシータにとってムスカは敵で、理解し合うことは不可能だった。ドーラとは仲間になるが、そこに葛藤や迷いは、描かれなかったと思う。
魔女宅では、少女が他者との関係を模索する姿があった。分かり得ない他者というより、キキ自身が自分を取り戻し成長するに伴い、他者は仲間になっていった気がする。要は、深くは描かれていないのだ。成長したら上手く回るってもんじゃない、と当時、僕は思った。しかし、成長するのは大事だ。成長したから上手く回せるっていう面もある。
紅の豚では主人公自身が、豚になって世界の他者になっていた。しかし、豚は何故か世界によく馴染んでいるように見える。なんというのかな、豚は、たぶん、ジーナさんにとっての他者になったのだ。自分にとっても他者になったというか。まあ、君生きの大伯父に近いキャラなのかもしれない。
もののけ姫は、他者ばかりが集まった作品という気がする。アシタカとサンは、予め他者どうしで、最後まで他者だったように思う。あれは、そうした物語だった。両者は既に確固たる大人であり、自分の世界があるのだ。
千千、子供が他者だらけの異界に放り込まれる話で、まあ、サバイバルだ。しかし中には助けてくれる人もいる。なんというか、必死なので、泣いたとしても悩んでも内面的な葛藤に目を向ける暇はないような気がした。そして、そういうタイプの物語でもない。
ハウル、、、わからん。実はよく覚えていないのだ。意味不明だったという記憶はある。
ポニョ、こっちも詳細はよく覚えていない。子供が人魚と将来を誓い合うというアナーキーな話だ。たぶん、難しいことは考えてない。
風立ちぬは、大人の映画だ。君生きに無いものがここにある。そして、君生きの主題はここには無い。
10月1日、追記。
ハウルを見直してみた。なんで意味不明だと思ったのか、まったくわからない、、、
思いっきりエンタメに振ってると思った。そして、傑作かも、と思った。、、今の時代のせいかもしれない。
2025.08.24.追記。
けっこう以前にポニョを観たので追記しておく。
ポニョは絵本の世界だ。それは背景の書き方がそうなのだ。
そして、これは戦争の映画だ。何故かわからないが、そういうイメージを持った。
アナーキーだという印象は変わらない。
意外にこういう気持ち悪くて変な映画は嫌いじゃない。
どうだろう。
こうしてみたら、意外に、君生きに近いのは、紅の豚なのか。
ジーナさんとフィオ、なつこさんとひみちゃん、世代が違う女性2人が主人公に絡むし、物語の最後で、豚は人に戻り(一瞬だけど)、真人は上の世界に戻り、大伯父の世界は崩れる。ひみちゃんはキスはしなかったけど、それに近いことを言ってのけた。そしてたぶん豚がジーナさんを訪ねたように、真人はなつこさんの息子になる。
いやいや、そんなバカな。全然違う話じゃん。
まあ、でも、そういうことがあると言っても通用するかも知れん。それぐらい君生きは分かりにくい。
しかし、こんなんでまとめになるだろうか。
収拾がついた気がしない。まあ、いいか、である。
収拾が付かないところになんだが、
6)ひみちゃんが上の世界に帰るために真人と会う必要があったというアイデア、について。
これも、豚がフィオのキスで人に戻るというのと、位置付けとしては同じなんだね。
まあね、男の子はね、単純だからね、それでいいかもしれないんだよ。
でも、うーん、、、
女の子ってそうなんかね?
息子がいい人だからって、火事で三十路?で死ぬ現実に戻るだろうか。女の子だったことがないので分からないけど、、、
ひみちゃんは、火事で死んだ大人のひさこさんと、母を震災で亡くしたひさこちゃんが、一体化したものだから、むしろ、大人のひさこさんが、息子の様子を見て安心したことのほうが、上の世界に帰ろうという気持ちになる理由としては、大きいのではないかと思った。
つまり、成仏出来るってことだ。
ここで怖い考えが。
真人が情けない奴だったら、ひさこさんは自分の世界に帰らないかもしれない。
そうなったら、あの世界、上の世界が崩壊する、かな。
タイムパラドックスというやつだ。
それとも、どんな愚息でも、かわいいって言ってくれるんだろうか、、、
まあ、それならそれで、しかたがない、ということかもしれない。
Sep 16, 2023
ジブリの「君たちはどう生きるか」を俺はどう楽しむか(レビューその3)
さて、3回目のレビューなんて、まさか書くとは思わなかった。
間が空いてないし前回のに追記してもいいかと思たんだけど、長々なるし、いよいよ読みにくくなるだろうしで、別枠にした。
といっても、今回は少なめなんだけど。
過去のレビューはこちら。
ジブリの「君たちはどう生きるか」を観て
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230818a.html
ジブリの「君たちはどう生きるか」2回目を観て(風立ちぬとアーヤと魔女もちょびっと)
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230914a.html
20日、追記。
うちのレビューを読もうかという人へ。書かれた順番に読まれることをお勧めする。
最初のは「混乱して、分からんことがあるなりに書いてるなあ」というレビュー。
2つめは「見落としを確認して、言い訳を書いてるなあ」というレビュー。
3つめは「幻惑されてたことに気付いて、多少は考える頭が戻ったかなあ」というレビューだ。
しかし、内容は概ね重なってないので、3つでセットだし、そのほうが内容を理解しやすいと思う。
なお自分用のメモでもあるので、今後も何か思い付いたら補足を追記する。
27日、追記。
4つめのレビュー。いちおう、まとめ。
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230927a.html
なんというか、初回観て、2回目観て、ずっと、何かしら考え続けてるんだね、僕は。
こんなん分かんないから、で終わらせたっていいのにさ。
たぶん、考え尽きて気が済むまで、止まらない気がする。
穿り返さないでいられないのは性分だろうから、しかたない。この映画でどう楽しむか、やってみるか、ということだ。
以下の雑文は、個人的な読み取り、解釈、感想文で、駿の思惑とは全く異なる可能性があるので(まあ、今迄のもそうだが)、注意喚起しておく。
アニメなんてものは観た人が勝手に面白がり、曲解でも何でもすればいいものだと思ってるので、宜しくお願いする。

さて、前回レビューを挙げた後、気になることが出てきた。
「君たちはどう生きるか」って、初版当時には真人は生まれてたのか?、ひみちゃん、もとい、ひさこさんは、何歳ぐらいだったんだろう。
その辺、時系列はどうなってるんだろう、ということだ。
年令など適当に目星をつけて、軽い気持ちで年表を作った。
そしたら、さらに気になり始める。
ひみちゃんも、火事で母親を亡くしてる。
多分それが、大伯父の世界に入って戻れなくなった原因だ。
真人と同じ年頃だった頃で、というと、1920年代前半、、何があった、、、
関東大震災だ。
2024.03.20. 追記。
3月17日に3回目を観て気付いた。「ひみちゃんも、火事で母親を亡くしてる」という上記記述には、根拠が無い。
これは僕の聞き間違いか何かで生じた勘違いで、ひみちゃんの母親の死因を特定することは出来ない。
だけど、ひみちゃんの母親が関東大震災で亡くなっているのではないかという想像は、していけない、というわけでもないと思う。以下の文面はそういう解釈で書かれたということにしておく。
以下、その年表。
22日、追記。
他のサイトのレビューで、サイパン陥落の1944年に疎開したと書かれているのを見た。
僕はそれは気付いてなかったので、年表を修正することにした。
| 年代・出来事 | ひさこさん | 真人 |
|---|---|---|
| 明治維新 石が降ってくる | ||
| 1923 関東大震災 | 13、4才? 1年神隠しになる | |
| 20才頃、結婚 | 誕生 | |
| 1937 盧溝橋事件 君たちはどう生きるか、初版 | 27、8才? | 5、6才? |
| (1941.01. 駿 誕生) | ||
| 1941.12. 日米開戦 | ||
1943 | 火事で死去 34、5才? | |
1944 | 13、4才? 塔の下の世界に行く |
|
| 1947 | 東京に戻る |
今年は100年になるというので、テレビで関東大震災の特番をやってて、いくつか見た。
どのようなものだったのか、正直、殆ど知識は無かったんだけど、大変恐ろしい災害だったこと、そして虐殺のこと、のちの人心にも大きく影響したであろうことが、この年令になって特番を見て、ようやく知った。
関東大震災は「風立ちぬ」でも取り上げられている。そういう視点があるか無いかで、風立ちぬを見ていても見え方が違う。
今回、年表を作って、ちょっと、背筋が冷たくなった。
ひみちゃんは、あの災害に巻き込まれて、母親を失ったのだ。
なんだろうね、駿は何でこういうところを隠すのか。
どこかで誰かの台詞に挟み込んでおけば、ずいぶん分かりやすくなるのに。
まあ、素人の言うことだが。
さて、こうなってきたら、ということで、他にも書き込んでみた。
真人が大伯父の世界に呼ばれ、あの世界が壊れたのは、終戦の年だ。あの世界が壊れて、その後、終戦になっている。
年表を修正したので、このあたりの文面は間違いということになる。
よくよく考えてみたら、終戦の夏に戦闘機の風防を増産しているわけがないのだ。
書き直すのも面倒なので、そのままにしておく。
あの大伯父の世界は、明治維新頃から終戦まで、存在したということになる。
悪意がある、石の力で。
あの世界、死者がたくさんいるとキリコさんは言った。
海に浮かぶ多くの船、あれは、軍艦だ。各々に死んだ船員がいるのだろう。
紅の豚で出てきた、高い空を雲のように浮かんで飛んでいく戦闘機たち。あのイメージだ。
そうか、ヴァルハラだ、、、
https://en.wikipedia.org/wiki/Valhalla
wikiの日本語版から引用すると「この宮殿には、540の扉、槍の壁、楯の屋根、鎧に覆われた長椅子があり、狼と鷲がうろついている」とのこと。
いや、ペリカンとインコなんですが。
扉はたしかにいっぱいある。しかし槍の壁、盾の屋根は覚えがない。
だとしたら、
ワラワラたちは、なんなのか。
死んだ兵士たちが、また生まれていく(もしかしたら、お国のために死ぬために)。
そうだとしても、生まれゆくことは祝福されること、かな。
ワラワラに魚を食わせるキリコさんに、真人と同じ悪意の傷がある。
明治から終戦、日本は富国強兵。
ペリカンは言った、何も食うものがない、ワラワラしかないと。
一方、インコ達は豊かだ。赤ん坊を孕んでるもの以外は、なんでも食うらしい。赤ん坊は大事だ。お国のためなのだから。
それ以外の者は、食ってもいい。何を食ってるんだろう、、、
なにしろ、ペリカンが食えないものを食っているのだろう。


ペリカンは地獄だという世界で、インコはのびのび暮らしている。
あの世界がそういう世界だとして、
ならば、石に含まれた悪意は、たとえば、軍国主義、かな。
悪意がない13個の石は、遠くを探して持ってきたと大伯父は言った。なんだろうな、、、
こういうのは、パズルを解くような面白さがある。
それが、実際に作品を理解する助けになるかどうか分からないけど。
それに、理解出来たから良いというものでもないだろう。理解した結果、つまらないということになるかもしれない。
まあ、そうなったら、なったってだけで、大した意味はない。
しかし、せっかくなので、ちょっと考えてみた。
年表に戻って、ひみちゃん(子供の頃のひさこさん)が神隠しにあっていた期間が1年。
そして、ひさこさんが亡くなって、真人が塔の下の世界に行くのに1年だ。
一致している。
たぶん、ひさこさんが亡くなってから真人があの世界に行くまでの期間によって、ひみちゃんがあの世界で過ごした期間の長さが決まったのだ。
時期が異なるけど、そういうのが問題になる世界だとは思えない。
真人の夢で、ひさこさんが亡くなる時に炎の中から真人に何か言う。
2回観たのに、よく覚えていないのが残念だ
なんでひみちゃんが火を操れるのかということになると、ひさこさんが助けていると考えたら辻褄が合う(あうのか)。
ひみちゃんの母親も、もしかしたら噛んでいるのかもしれない。
成り立つのかね、こういう構造、、、
エントリーアップして早々に追記。
ひみちゃんが、真人から母が火事で死んだと聞かされても驚きもしないのは、ひさこさんと一体化しているからだ。
ようやく気が付いた。ずいぶん時間が掛かってしまった、、、気付いたら、簡単な話だと思う。なんで気付かんかったかな。
8月19日、エントリー末に筆を置くとも書いたし、ほどほどにしたいんだけど、更に追記。
ひみちゃんとひみこさんが一体化していることに充分に意識が向かなかったのは、
僕にとって、それは気持ちが良くないことだったからだ。
駿作品が内包するマザーコンプレックス表現については、過去に多くの論者によって語られてきている筈だ。
そうした論説を、僕も読んだことはあるが、ぴんと来なかった。そういう見方もあるんだね、という受け止め方だ。
君生きは、過去作品よりも、母子関係を明確に題材にして作られている。そこに触れなければ、もしかしたら理解できない、かもしれない(まあ、理解のしようなんて個々人の勝手でいいとも思うんだけど)。
ただ今回、あからさまに作られた作品に触れることになり、
今日、初めて自分でも気付いたが、どうもそういうのは、僕は苦手らしい。
例えばエヴァンゲリオンなら、物語の中の話、あるいは、碇君やゲンドウの個人的な話、として、客観視できるというのか、突き放して自分とは関係のないこと、というニュアンスで作品に触れることができた気がする。
君生きは、そうではない。
気が付いたときの違和感の強さが、エヴァよりずっと強いのだ。
えげつない言い方をすれば、気が付いたら母子相姦させられていた、とでもいうような。
エヴァは、そういう話だという前提が予め観客に共有されている。
君生きにはそれがない。
なんだか、わけがわからないままに、巻き込まれた感触がある。
気付ける人は映画を見ながら気付くんだろうけど、僕のようにそうした論説がぴんと来てなかった人には、充分な免疫がないのだ、と思う。
いや、それだけじゃないかな、、、
若い頃の方が違和感少なく受け止められたのではないかという気もする。
より母親と近かった子供の頃の感覚を、まだ心の底が覚えていたかもしれない。
それにしても、僕がこのことに2ヶ月気付いていなかったことが、意外だった。
でもまあ、しかたがない。
この映画を楽しむには、いろいろ骨がいるということだろう。
21日、追記。
そういうわけで、僕が思っていた以上に、ひみちゃんとひさこさんが一体化してるということなら、
ひみちゃんが、真人から「母さんは火事で死んだ」と聞いても、けろっとしていて不思議はない。分かりきったことだからだ。
もしかしたら人によっては、ひみちゃんは母の化身そのものだと最初に思って、実は過去から来た若い頃のひさこさんで帰らないといけないということに驚くかもしれない。
一方で、真人は、どうやらひみちゃんを母親だと認識したまま、であるらしい。
劇中、真人が得られる手がかりは、ひみちゃんの「(なつこさんは)妹だ」という台詞だけだ。これを聞いても真人は驚きもしない。
真人も、最初から、分かっていたのかもしれない。
むしろ、分かってるから、母は火事で死んだと言えるのだ。
あそこは、そんなでも、まったくおかしくない世界だ。
2024.03.20. 追記。
3月17日に3回目を観たのだけど、「真人は驚きもしない」と上に書いているが、ちょっとだけ驚くような、「いもうと?、、」とつぶやく場面がある。でも、それだけで、だからどうということもなく、話は続いていくのだ。なんというんだろう、この映画の登場人物たちは、一を聞いて十を知るような理解力、認識力を持っているとしか思えない。台詞で説明をしない。観客は、おいてけぼりなのだ。
さて、、、
なんでこんな、分かりにくい状態にしてるのか。
わざと、分からないようにしてると、前のエントリーで書いたけど、、
自分を顧みて思う。
母子相姦的な話であると、明確に分かったら困るから、分からなくしてるのだろう。
分かったら困るのは、観客だけじゃない。むしろキャラクターたち自身が、困るのだ。困りまくるに違いない。
駿は、この世界を構築するために、とてつもないバランスをとって脚本を詰めているんだと思う。
それこそ、大伯父が積み木を積むがごとく。
どっひゃー、、である。
番外っぽいがキリコ婆さん。1945年に75才ぐらいだとしたら1870年生まれ、大日本帝国憲法の発布が1889年。このとき19才。1873年、徴兵令。婆さん、3才。
ていうか、このぐらいの婆さんは、ふつうに子供を戦争にとられてるのだ。

話は変わる。
僕は宮崎作品に子供の頃から接してきているが、好きなキャラを選べと言われたら、コナンとラナになる。
駿は、より複雑な内面を持つ興味深いキャラを何人も生み出してきているが、厳選して選べと言われたら、僕の場合は、そうなってしまう。
今回、真人とひみちゃんは、なんだかその2人が重なるのだ。
キャラの年令がほぼ同じなことが理由ではない。それならラピュタも当てはまる。
性格が似てるとは、全く思えない。のだが、、
真人の「なつこさんを連れて帰る」という、あの妙な一途さが「ラナを返せ!」と叫ぶコナンと妙に重なる。げしげし弓矢を作ってしまう戦闘力の高さも重なるのかな、なんか、決断が早い。実戦向きなのは戦中の子だからだろうか。
ひみちゃんとラナって、どう重なってるんだろう、、、特殊能力があるとこか。
いや、じつは囚われの身で、大伯父というラオ博士がいて、背中を押されて、真人と帰っていく。そういう構造が生む何かが、何かなのだろう。上手く言えん。
こんな感じかな、、、
こういうのは、映画を楽しんでると言うんだろうか。
囚われてるのも同然な気もする。しかし、自分の意志で考えたり調べたりしてるのでなあ、、、
しかし、この辺で、一旦かな、筆を置くことにする。
9月18日、追記。
一部、改行を修正し、文面上の内容の重複を削除した。
更に追記。彩りでいくつか画像を表示することにした。ジブリから提供されている。
Sep 14, 2023
ジブリの「君たちはどう生きるか」2回目を観て(風立ちぬとアーヤと魔女もちょびっと)
君たちはどう生きるか(以下「君生き」)だけど、12日に2回目を見てきた。
前回が7月18日なので、2ヶ月足らず、空いている。
そろそろ見るか、と思うまで、そのぐらい掛かったということだ。
初回を観てのレビューが下記エントリー。2つ目を書くとは思わなかった。
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230818a.html
3つ目を書いてしまった。
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230916a.html
20日、追記。
うちのレビューを読もうかという人へ。書かれた順番に読まれることをお勧めする。
最初のは「混乱して、分からんことがあるなりに書いてるなあ」というレビュー。
2つめは「見落としを確認して、言い訳を書いてるなあ」というレビュー。
3つめは「幻惑されてたことに気付いて、多少は考える頭が戻ったかなあ」というレビューだ。
しかし、内容は概ね重なってないので、3つでセットだし、そのほうが内容を理解しやすいと思う。
なお自分用のメモでもあるので、今後も何か思い付いたら補足を追記する。
27日、追記。
4つめのレビュー。いちおう、まとめだ。
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230927a.html
2回目を観たのは、初回に観た時に間違えたり記憶が曖昧だったことを確認しようというのがあったんだけど、充分に出来なかった。メモを持っていくのを忘れたのだ。だから今回も記憶頼りだ。それでも、まあ、収穫はあった。
予め書いておくけど、この映画は「何も知らない状態で観る」のがデフォルトらしい。
駿が意図することに乗ったほうがいいのかな、と多少でも思ってる人は、こんなエントリーを読む前に、映画館に行くべきだと思う。今回、2回目を観て、けっこうそれは大きいと思ったので、ここに書いておく。
さて、2回目を見る前に「風立ちぬ」をレンタルして観た。
何となく、観ておく必要があると思ったのだ。
公開は10年前だ。何でその時に観なかったのかははっきりしないが、たぶん子供がまだ幼稚園で小さくて、忙しくて観なかったのだろう。必ず全部観るという程の熱心なファンじゃないので、そのままになったんだと思う。
しかし、なんだかな、あのポスターが気に入らなかったというのはあるかも。とっちゃんぼうやが飛行機を見上げて、なんだこの中身無さそうな主人公は、という印象だったのだ。
まあ、機会があったら見るでいいかも、と思っていた。変な世評ばかりだったし。
実際に観てみたら、普通にすごくいい映画だった。
駿は当時これで引退と言ってたけど、立派なものじゃないか、と思った。
主人公は、ポスターから僕が受けた印象とは全く違って、すごくしっかりしたいい奴だった。
風立ちぬは、機械とロマンスと歴史の映画だ。現実の映画であり、生きざまの映画だ。
君生きには、それらがない。ファンタジーと少年と母の話だ。夢の中、心の中の話であり、生きざまから逃亡した映画だ。
つまり2作で対になっている。
片や普通にすごくいい映画で、片や意味不明な問題作だ。
いい対である。
人は片方だけではやれないだろう。
僕は未来少年コナンで宮崎駿を意識した人間なので、足りない石はSFだと思ったりするけど、どうなんかな、さすがに今の時代、SFを駿に要求するのは厳しいかな。
まあ、君生きは宇宙から来た何かが、なので、ギリギリSFなのかもしれない。大伯父周辺の雰囲気はSFっぽい。
このエントリーでは、前回に書ききれなかったこと、新たに思ったことを書いていく。
順不同で箇条書きみたいになるので冗長だろうが、自分用のメモなのでいいのだ。
まあ、ネタバレばかりになる。
しかし、いざ書こうと思ったらどこから、と思うんだけど、まあ、一番に気になってたとこから。
2024.03.20. 追記。
3月17日、3回目を観てきた。そこで確認したことがあって、このセグメントには、間違いがあることが分かった。
書き直すのは面倒なので、説明は後述する。
ひみちゃんのこと。
主人公の真人が「なつこさんを探している」と言った時に「妹だ」と言っているのを確認した。
これに対して真人は、ひみちゃんが母親だと、明確に認識したのかどうか、はっきりしない。そのまま曖昧なままストーリーが進んでいく。
真人はひみちゃんに、自分の母親は火事で死んだと話している。ひみちゃんに未来を宣告したことになるのだ。美味しいジャムパン食ってるときだったと思う(このあたり文脈を忘れている。メモを忘れたのが悔やまれる)。でも、ひみちゃんはけろっとして聞いていて「私の母親もそうだ」などと言う。
そういう話じゃないだろ、分かってんのか、君たち。
いろいろ考えて、補足を追記(9月18日、多少、分かりやすいように書き直した)。
真人が母親は火事で死んだと言ったとき、ひみちゃんに未来を宣告したことには、実はまだ、ならない。
観客から観たら、まだこの時点では、ひみちゃんが真人のことを「自分の息子だと認識していない」可能性が、ある。
(逆に言えば、観客にも、ひみちゃんがひさこさんだという確信は持てない:補足更に追記:だって、なつこさんの姉が、ひさこさん1人とは限らない)
ひみちゃんの立場から見たら、
真人から、なつこさんが真人の父親と結婚している、と聞いただけでは、
「真人の父親の前妻が、なつこさんの姉=ひみちゃんであり、だから真人はひみちゃんの息子」という認識は、
まだ、出来ないのだ。
だって、父の前妻がひさこさんだなんて、真人は一言も言ってないのだから。
(考えてみたら厳密に言えば、前妻がひさこさんだとしても、真人がひさこさんの子とは限らない)
しかし、その後、石の産屋で、ひみちゃんは真人の母であると宣言している。
この時点で、
どうやら最初から、ひみちゃんは真人が息子だと認識していたらしいことが、観客から見ても、はっきりした。
だったら、ひみちゃんは、真人の「火事で死んだ」という発言に、驚かないわけがない、のだけど。
なんか、ややこしくて、僕がどこか間違ってるかもしれない、、、
いや、この際なので敢えてここに追記しておくが、ひみちゃんから、真人に、母であると告げる場面は、劇中に全くない。はずだ。僕が2回も観てるのに見落としているのでなければ。
補足、ここまで。
というか、初見のとき、この時点で僕は、ひみちゃんが真人の母だと確信していなかった。妹?どゆこと?、母なの?みたいな感じだったのかな、真人がそれをちゃんと聞いて知ってるかどうかすら、僕の中では曖昧になっている(というか、こんな会話が交わされる時点で、真人には伝わってない認定が僕の中では出来ていたと思う)。
なつこさんの石の産屋で真人が気を失い、ひみちゃんが母だと明言したことで、僕はようやく明確に認識ができた。
初見は、そういう感じで、いろいろ曖昧だったということだ。
今回は最初から理解して観ているので、全く受ける感触が違った。
これは実は、この映画の大きなトリックなんだと思う。
2024.03.20. 追記の続き。
何故か僕は、2回も観たのに、真人はひみちゃんに「母さんは火事で死んだ」と告げたとばかり思っている。
それに対して、ひみちゃんが「私も」と応えていると思い込んだ。
それは間違いだったと、3回目を観て気付いた。
実際の画面では、真人は「母さんは死んだ」としか言っていない(はっきり火事で死ぬと告げるのは、それぞれの現実の世界に帰るまぎわになってのことだ)。
何でこの時点で告げたと思い込んだのか分からない。
ひみちゃんがあまりにも平気の平左で真人の言うことを受け入れるので、最初から知ってたんだろうと認識してしまったのだろう。
さて、、、
そうした経緯で僕は、ひみちゃんの母親も火事で死んだという、僕だけに通じる設定を抱え込んだ。
でも僕は、勘違いか聞き間違いから生まれた、この根拠が無い思い付きのような設定が、僕なりの解釈の中ではしっくりと納まってしまった。
その流れで3つ目のレビューも書いている。
そちらにも注記を入れておこうと思う。
閑話休題だ。
最後に各々の世界に帰るとき、
真人はひみちゃんに、帰ったら火事で死ぬことになるから、こっちに来いと告げる。
ひみちゃんは、真人の母親になるならそれでもいい、と言って自分の世界に帰っていく。
あんたら、全部わかってたんかい、、、
どうにも、こんな重大事が宙ぶらりんなまま話が進んで、最後にパタンとケリがつくという、最初に観た時は、僕はこれにはすごく混乱したようで、どうなってるのか十分な認識ができていなかった。
脈絡とか理性的な筋道とか考えたら説明しがたい。
だって、真人にとっても、ひみちゃんにとっても、驚いておかしくない、というか驚くのが普通な話で、物語の進行がストップするような案件だ。
納得がいく説明は、夢の中などではそういうのは関係なくなる、現実に帰るときに、夢から目が覚めるときのように、思い出すんだろう、というような。だから、自分たちの世界に帰る直前に、あのこと分かってたんだ、みたいなことを言い出すという。
そういう説明で、自分を納得させている。
大伯父が作った世界は、受け入れがたい現実を、柔らかな包帯に包むような、そういう世界なんだと思う。
主人公の名は「まひと」。麻痺してる人だ。夢の世界に行くということは、覚醒から遠くなる。ファンタジーとはそういうものだろうと。
そこに「母」がいるのが真人の夢だ。
真人は、青サギの誘いに「母さんは死んだんだ!」と。キリコ婆さんが罠だと言うのに「知ってる」と。
彼は、現実を受け入れないといけないことを知っている。
それでも、大伯父が作った世界に踏み込んでいく。
なつこさんを、取り戻さないといけない。それは、現実を取り戻すことと同義だ。
現実の母さんは、死んでいる。
夢のような世界で、まだ生きている母、ひみちゃんと出会った。
夢から覚めたら、忘れないといけない。
しかし、石を持ち帰ることは出来る。
真人が持ち帰った石、僕はこれが「強力なお守り」なんだと思っていたけど、画面上、青サギはキリコ婆さんの人形のことを言ってるように見える(実際、キリコさんは人形を真人に手渡すときにお守りだと言った。しかし、その場に青サギいたから知ってるんじゃなかったのかな、、)。
青サギは、真人の記憶があることを訝り、真人がポケットから出した人形と石を見て、強力なお守りだと言い、石を持ってくるなんて、これだから素人はだめだと言いながら、じきに忘れるからまあ良い、あばよ友達、と言って飛び去り、直後に人形はキリコ婆さんに戻る。
あれ、石はどうなったんだろう。
つまり、強力なお守りがあったから記憶がある、という文脈に見える。
しかしそれが、人形なのか石なのか、そこは実は明言されていない、ように見える、かな。
どうなんだろうね、、、
エンディング、真人は東京への出立に際して「君たちはどう生きるか」を鞄に詰めて、部屋を後にする。2年経っても、彼にとって大事な本であり続けている。
大伯父の提案を受け入れ、ひみちゃんがいる世界を維持することは、母が遺してくれた「君たちはどう生きるか」を、真人が生まれて母と共に過ごした10数年を、捨てることだ。
そういえば真人が石を拾ったのは、
大伯父に会うため、流星雨の夜空の下を、ひみちゃんと一緒に、歩いていた時だった。
このあたり、なんというのだろう、時間軸とか空間とか、超えた何かを感じる。一瞬は永遠、永遠は一瞬だ。上手く表現できない。説明できなくていいような気もする。
ひみちゃんは、彼女の現実世界に帰る。
帰ってもいいと思えたのは、
真人と会うことが出来たから、真人を生みたいから帰るということなら、
まあ、若干の物議を醸しそうなラブストーリーという見方も出来る。駿のコンプレックスがどうのという話もあるが、ここでは深入りしない。アングラファンタジーなら、ああ、そうなんか、と許容される話、と思う。
大伯父の世界にとらわれた鳥たちと、自分の意志で留まっている人間たち。
真人となつこさん、ひみちゃんは自分の世界に帰り、キリコさんは婆さんに戻った、のかな。インコとペリカン、青サギも帰った。大伯父の世界が壊れて、生きる者は生きる者の世界に、死者は死者の世界に、其々帰ったということなのだろう。
真人がなつこさんと戻ると決めたとき、ひみちゃんは戻らないという決断も出来たのか、それは大伯父の世界と一緒に滅びるということ、なのか、、、
もしも、ひみちゃんが現実世界に帰らなかったら、真人が生まれてこなくなる。
これはこれで困る。
この辺り、謎だ。
ひみちゃんは生きている人なので、あの世界が滅びたら、自分の世界に帰るしかないのかな。
笑って帰れたので、良かったのかな。
真人から見たら、母に夢の世界で認められて、過去を受け入れて帰ることが出来た、というストーリー。
ひみちゃんから見たら、将来出会う息子と会って、未来への希望を得て帰ることが出来た、というストーリー。
なんだけど、、
思いついたこと。
なんで真人は、呼ばれたのか。
実は、ひみちゃんを帰すため。
ひみちゃん、じきに帰るだろうと大伯父は思ってたけど、居付いてしまった。早晩崩壊する彼岸の世界に。崩壊に伴って、本人の意志ではなく帰らされることになるのは、たぶん、ひみちゃんにとって良くないのだろう。
なつこさんが、真人が、大伯父の世界に呼ばれたのは、大伯父が描いたシナリオ。
たぶん、あの世界に親和性が高くない人は、呼べないのだ。
最初は真人だけ呼ぼうとしたが、無理だったので、なつこさんを引き込んで人質にした、、、
違う、最初に呼ぼうとしたのは、なつこさんだ。ひみちゃんの妹だから。
真人が来る前に、なつこさんと青サギの間に駆け引きや闘いがあったのだろう。そう考えたら、弓矢で真人を助けるときの手練っぷりに説明が付く。
そして、それは結局、成功しなかったのだろう。
なつこさんは、こうした不可思議なものごとは、夫には何も話していないのだろう。姉がそうだったように。まあ、ふつう信じられないだろうから。
そこに真人が来る。
大伯父のターゲットは妹から息子に変わった。
そういうことなのではないか、、、
30日、追記するのをを忘れていたので追記。
他のサイトのレビューで、弓矢で真人を守ったのは、夢の中での出来事という説明があった。
そのほうがたしかに、より整合性がある解釈だと思う。
その説明に沿えば、大伯父が最初に呼ぼうとしたのはなつこさんで、真人が来る前に青サギと接触があった、という考えは、必然性が薄いということになるかもしれない。
ひみちゃんに、真人を帰さないといけないと言っていたり、真人が石を受け取れない、現実に帰ると言った時に、強く引き止めもしない。なんでかな大伯父、と思っていたけど、それがシナリオ通りだからなのだろう。
どうだろうな、、、
こんなこと書いてて、いいのかしら。
いくつか小さい話というか、メモ書きを。
絵画をモチーフにしていると思われる画面がある。

ベックリン:死の島
https://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_the_Dead_(painting)
ヒトラーが所有してたことがあるそうだ。「風立ちぬ」でも使われている。

ターナー:The Fighting Temeraire, tugged to her last Berth to be broken up(解体されるために最後の停泊地に曳かれてゆく戦艦テメレール号)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fighting_Temeraire
海と船、空のイメージ。雲の形は違うが、色遣いや雰囲気は非常に近い気がする。
絵のタイトルがちょっと凄い。
大伯父の内心を語っているようだ、というのは読み過ぎか。

ゴヤ:砂に埋もれる犬
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dog_(Goya)
大伯父が石を積んでいるあのだだっ広い部屋のイメージ、何処かで、と思うのだけど分からない。なんとなくこういう雰囲気の絵が、何かなかったかなと思うのだけど。
僕が思い出せる絵のうち、イメージとして一番近いのが、黒い絵の犬。
他にも、これは元ネタがあるんだろうな、見覚えがある気がする、という画面はあるが、分からない。
画面ではないが、真人が下の世界に降り立ったときに、門に書かれていた言葉「我を学ぶ者は死す」について、画家、中川一政のエピソード。他に出典はあるらしい。
https://www.city.komae.tokyo.jp/koho/128591.html
25日、この項目、いくつか補足追記する。
https://www.city.komae.tokyo.jp/koho/128591.html
小池邦夫のうちあけ話 6 絵手紙のひと 広報こまえ(狛江市)から、引用。
僕が師と仰いだもう一人は、洋画家の中川一政さん(1893~1991)です。(中略)
歩き方や話し方まで似てきた僕にある日、中川さんが言いました。「我を学ぶ者は死す」。
中川氏は、薔薇の絵を沢山描いたらしい。
https://ameblo.jp/moji-taro/entry-12816540105.html
「君たちはどう生きるか」ネタバレ解説3 地獄の門、バラの謎、「我を学ぶ者は死す」と墓の主の正体 | MOJIの映画レビューから、引用。
この言葉の出典を探ってみると、林房雄の「四つの文字」という小説に行き着きます。
林房雄は1903年生まれの小説家・評論家。
Youtube上に「四つの文字」の朗読が上がってるので、聞いてみた。
語り手である「私」は、南京政府の大臣である男を評して「虚無」だと言っている。
虚無が掲げていた四文字が「学我者死」。そして、戦争が終わると大臣は自死する。たぶん決められていたことであるかのように。
決められていたかのように崩壊する大伯父が作った下の世界、そして大伯父自身と重なる。
石の墓の中に封印されているものは、それこそ虚無か。
虚無という言葉は、漫画版ナウシカにも出てきた。しかし、ナウシカ作中で墓所がいう虚無と、四つの文字で言われる虚無は、言葉は同じでも意味する中身は異なるように感じる。しかし、はっきりしないので説明はしないが。
下の世界の入り口直下に、虚無?が封印され、あの世界が作られている。
あの世界が崩壊したら、多分、墓に封印されていた何かは、開放されるのだ。
どこにいくのだろう。
もしかしたら、インコの糞になるのだろうか。
糞をするということは、生きているということなのかもしれない。
ペリカンは、キリスト教において、全ての人間への愛によって十字架に身を捧げたキリストの象徴。
胸に穴を開けてその血を与えて子を育てるという伝説から、とのこと。
自己犠牲の象徴である鳥が、生まれに行く者たちを食うというのがどういう世界観なのか、、、
https://en.wikipedia.org/wiki/Pelican
真人とひみちゃんが大伯父のいるところを目指す際に、夜空に流星群がみられていた。
宮沢賢治の銀河鉄道の夜に出てくるペルセウス座流星群のイメージ。
日本ではお盆と重なる。
そういや、ひみちゃんがワラワラを守るときに花火を上げてたなあ。
鳥の糞は、初回の時ほどには驚かなかった。なんだか少なくなったように感じた。見慣れたのか。
まさかと思うが、流星雨と糞の雨を重ねるとか、そういう意味はないよなあ、、、
今回、主人公が「真人:まひと」だと確認した。
初回のあと、なんていうんだったっけ?となって、だから前回のレビューは「主人公」で通している。ネットで調べたらわかるだろうって?、そんなことするのは、なんだかすごく口惜しいじゃないですか。
さて、 今回、2回目を観て、ある程度は理解して観ているので、そこに上乗せして観ていけばいいので、初回とは全く受ける感触が違った。前情報なく観たというのは、凄く大きかったんだと思う。
これは、君生きのトリックだと書いた。
前情報があれば、そういう覚悟なり得られた情報を支えに、実際に映画からの情報を上積みできる。
君生きはそうではない。
目の前の映画から得られるものが全てだ。
前情報全く無しで情報量の多い映画を観ると、幻惑される。
良くも悪くも、映画の世界に搦め捕られていくか、弾き飛ばされ離脱するか、どちらかだ。
ストーリー展開の情報が多く、隠されているものも多いし、画面からの情報もすごく多い。
こういう話はこういうふうに展開していくだろう、という予測が難しい。
脈絡なく意味深な台詞が投げかけられる(例えば、キリコさんから「死に匂いがする名前だ」とか)。エピソードも意味不明だ(例えば、なつこさんが弓矢で真人を救うとか)。
そのまま投げっ放しで、受け止める枠がこっちにはないので、わけが分からなくなっていく。
なんというか、そういう作りになっている。
多くの人達が分からないと戸惑うのは当然で、たぶん、それを魅力だと思えるかどうかなのだと思う。真人と一緒に暗い夢を見るような体験を、肯定的に捉えられるかどうか。
僕がアングラファンタジーと云ったのは、そういうことだったと思う。
穿った見方をするなら、回収できない伏線を放置することにしたのを誤魔化しやすくなるかもしれない。しかし、駿の映画ともなれば、理屈はどうとでも後付けできるもの、と今回、僕は思ったので、そういう消極的な方法論ではないだろうと思う。
21日、追記。なんでこんな分かりにくくしているのか、今更思い付いたので3つめのレビューに考えを追記した。
これは、真人とひみちゃんを救うために駿が仕掛けた大掛かりな罠なのだ。そこに観客もろとも落ちるがいい、ということなのだろう。
分かりやすい映画を見たかったら、風立ちぬを見ればいいと思う。
実際、今回初めて見たけど、とてもいい映画だと思った。昭和時代の日本の名画の伝統を感じる。
たくさんの飛行機、機関車、田園、街、工場、人々のくらし、震災、時代、夢、戦争、甘いロマンス、夫婦愛、、、
見どころは沢山あり、登場人物達はみんな愛おしい。
子供向けじゃないけど。
子供向けなら、アーヤと魔女もいい。
実は、駿が企画で最近のだというので、一応これもDVDを借りた。
世評は芳しくないのでどうかと思ったが、いやいや、これは面白かった。
何もメッセージがない。不機嫌、不穏当にシフトしたキャラクターたちがバタバタするだけの話で、みんなアーヤに優しくなって(よく見たら不機嫌だったサブキャラ達がエンディングではそうでもなくなってるんだね、、)お母さん帰ってきてよかったね、で終わって、なんにも後に残らない。
主人公の性格が最後まで程よく悪く、改心なんてするわけもなく、かわいい表情も見せるが基本アグリーなのもいい。
作業場の床の汚さや薬の悪臭の表現も上手い。こんなとこに居たくない感じが凄く伝わる。
一方、ジブリ飯はちゃんと美味そうだ。変なところで律儀だ。舞台はイギリスなのに。
すごく褒めてるけど、じっさい、過小評価されてるんじゃないかな。
何がいけないって、宣伝のキャッチコピーだ。Wikiからの引用だけど、
「わたしはダレの言いなりにもならない。」
「私のどこが、ダメですか?」
ダメでしょ、こんなの。
なんだか主人公の自立っぽくて自己評価がどうこうっぽくてメッセージあるっぽくて、胡散臭い。これで勘違いさせられた客が見て、何も残らないから駄作と言うのだ。
映画と客で全く価値観がずれまくっている。
しかし褒めといて難だが、2千円は高いかも。もう一押しかな。レンタルで200円で見るなら全然文句ない。
あ、子供向けなら、と書いたけど、あんまり道徳的なアニメじゃない。そういうのが嫌いなら向かないかもしれない。
へんな宣伝打つよりは、今回の君生きのようなやり方の方が、
誤解がなくて余程いいと思う。
アングラが作るファンタジー映画なら、そういうもんなので普通に宣伝すればいいのだ。しかし、君生きはジブリでメジャーだから、誤解されないアングラファンタジーの宣伝は難しいと思う。
とりあえず僕が思いつくのは、諸悪の根源であるキャッチコピーは、なし。予告編は、音なし。いや、音は久石譲のピアノのみとか。映像以外に全く説明がないなら、何とかなるかも。アメリカ向けトレーラーは、その辺り、いい線いってると思う。あれ見てもほぼ何も分からないという意味で。
与太話は、そんなとこで。
2回目を見ての評価は、とりあえず、この映画は好きだということだろうか。
しかし、もう少し分かりやすくてもいいのに、とは思う。
Aug 18, 2023
ジブリの「君たちはどう生きるか」を観て
お盆も過ぎたので、そろそろネタバレ気にせず考えたことを書いてもいいかと思うので書いてみる。
そうはいっても、それは見たくないという人もいるかもしれないので、下の方から書き始めている。
2回目を観てきたので、レビュー2本目を書いた。
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230914a.html
まだ観てない人は、こうしたエントリーを読む前に、1回観た方がいいのではないか、と思う。
さらに追記。
3つ目を書いてしまった。
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230916a.html
9月20日、追記。
うちのレビューを読もうかという人へ。書かれた順番に読まれることをお勧めする。
最初のは「混乱して、分からんことがあるなりに書いてるなあ」というレビュー。
2つめは「見落としを確認して、言い訳を書いてるなあ」というレビュー。
3つめは「幻惑されてたことに気付いて、多少は考える頭が戻ったかなあ」というレビューだ。
しかし、内容は概ね重なってないので、3つでセットだし、そのほうが内容を理解しやすいと思う。
なお自分用のメモでもあるので、今後も何か思い付いたら補足を追記する。
9月27日、追記。
4つめのレビュー。いちおう、まとめだ。
http://blown-lei.net/endive/blosxom.cgi/letterbox/20230927a.html

僕が「君たちはどう生きるか」を観たのは7月18日だった。以降、感想をX(もとツイッター)に書き込んでいるので、先ずは引用していく。
7月18日
ジブリの観てきた。 枯れてるのかと思ってたら逆だった。
詰め込み方が上手いんだろう。とてつもなく濃いが喰えた。ゲテモノ度が高い気がする。これが駿の誠意なのか。
タイトルは、もうちょっとましなのつけりゃよかったのに。投げやり感漂うぐらいが風通しがいいとでも。いろんな群れが出てくるなあと思った。群れるものと群れないものの対比。
8月7日
今回は音楽が良かった気がする。ピアノだけ鳴ってる場面が多かった。
8月9日発売なので聴いてみたい。あと今回は、音響が良かった気がする。効果音と言うのか。
いちいち生々しかった。
ただ、他の作品と比べる術が僕にはない。君たちはどう生きるかを傑作と呼ぶ気にはなれない。
そういうのは千千とかコナンとかカリ城とか、話の纏まりがあって訴求性が高くないと言いにくい。観る者に大して挑みかかるような作りになっていることが、過去作よりずっと、観る者に分かりやすくなってるんだろう、と思う。
極めて変な映画だ。観た者は、たぶん多くがなんじゃこりゃと思う。そう思ったときに、傑作という者とゴミという者が別れまくる。
そもそも、鳥の糞、多すぎ。
異物まみれの映画を僕等は突き付けられるのだ。
今までも異物が多かったけど、今回は現実もファンタジーも共に異物にされてる。
今回、オブラートが殆どない。メジャーな映画ではなくアングラな作りになっている。
考えてみたら、昔はアングラな映画が数多くあった。今回、ジブリがアングラ映画を作ったんだと思う。
ストーリーも昔のアングラファンタジー映画っぽい。そう、僕は懐かしいと思った。
20代の頃にこんな感触のをよくレンタルビデオで観た。アングラファンタジーなら、意味不明なタイトルも、エンディングの突き放しっぷりも、ありに見えてくる。
宣伝費はかけられない。下手な宣伝はできない。この奇妙な感触が、昔馴染んだものだと気付くまで、3週間かかった。
最近、触れることがなくなった。
世界が変わったのだろう。8月14日
この映画の周辺、勝手に理解しろ的に、昔のアングラ映画みたいに、情報がなくて、観た者を突き放している。
多分、暫くは何も出ない。うちの子とか見てると、分かりやすくてスピーディに話が進まないと見る気がしないようなのだ。
そういうコンテンツばっかりになってるのが、駿は嫌なんだろう。
こんな感じだ。
自分としては、決して否定的ではない。
世間では、パンフレットが発売されたが何も書いてない、詐欺だ、表紙も鷺だと盛り上がっている。駿達はそれ見てニタニタしてるんだろう。悪質である。アングラに似つかわしい。
思っていることの骨子はだいたい上記引用で済んでいる。
1回だけでは理解してないこと、気付いてないことがありそうなんだけど、2回目観るのは今はまだ気が進まない。いろいろ事実確認するとか、そういうことする映画じゃないという気がする。なんでか分からないが。アングラだからだろうか。
この後は、個別の事象について思い付きを書くので、いろいろ雑談だ。大したことは書いてない。
何かあったら追記するかもしれない。
序盤、オープニングから戦争で始まる。主人公の母親が焼け死んでしまう。
1年後、主人公は父親の都合?で転校になる。
転居先には、新たに母になるという人がいて実母の妹で、という。
そういう現実でしんどくて、という話が、大変なクオリティの画面で描かれる。主人公の表情も硬い。
エピソードがいちいちえぐい。
新たな母になるなつこさんは、対面初日にいきなり主人公の手を取って、子供がいると言い腹を触らせる。どうにも危ない人だ。
新居は非常識なぐらい古くてでかい屋敷で、そこに戦闘機の風防が多数、置き場がないからと父の指示で持ち込まれ並べられる。それを見て主人公は「きれいなものですね」と。そんな感想かよ。
主人公は学校では周囲からハブられ、喧嘩の後で自分で石を拾って側頭部に流血の自傷行為。父親が学校に持ち込んで騒ぎに。たぶん主人公の計算どおり。
まあ、そんな感じで、いちいちなんだかメンタルにグロテスクで違和感を増幅し神経に触る。
主人公に感情移入もしにくい。
なんか、いじけきってる。観客の感情移入を拒む雰囲気があるのだ。
駿、今回は手加減ないな、と思っていたら、、、
変な鷺がいて、主人公の部屋の窓から主人公に絡む。主人公は追い払うんだけど、その際に、この鷺、窓枠に大量の糞をしていく(脱糞するシーンはなかったと思う。飛び立った後に、窓辺が汚れているのが描かれている)。主人公は気付いてか知らずか、鷺が飛び去って直ぐに窓を閉めるんだけど。あれって、あとでおばあさんたちが掃除したんだろうな。
まあ、鷺って、そういう鳥というイメージあるけど、駿、それをアニメーターに描かすか(どういうやりとりがあったやら、、)。そして、我らに見せるか。どういう気で見せてるんだ、半ば擬人化した鷺なのに。
この時点で僕は、今回はやっぱり相当えげつないんだ、と思った。
観客に、気持ちよくなって帰ってもらおうという気は更々ないということだ。
しかしそんな殺伐たる雰囲気の中で、主人公は亡き母から送られた本を見つけて、読んで、涙する。
ここから、主人公が能動的に動き始める。
頑なな雰囲気がとれて、ガードが外れる。
なんというんだろう、この映画のメッセージその1は、本読め、ってことだろうと思う。本読んだらこれだけ自由になるんだよ、という。まあ、そういう場面。
大好きな母から送られた本だからだろうって?、そりゃそうだけどさ。
僕自身も10代にこの本を読んで、良い本だったという記憶はある。内容はほとんど忘れてしまっている。他者との繋がりについて書いてあったことが印象に残っている。印象だけが、残っている。
なんつうか、ジブリ映画のメッセージ性ってあるにはあるんだろうけど、個人的にはそんなのは映画の良し悪しには関係ないと思う。そして、個人的な感動の鍵というのは人各々で異なるものだろう。
閑話休題。
中盤、主人公は、鷺を追って、異世界に呑み込まれていく。
いろいろなイメージ、オマージュが描かれる。それらに見入るだけでも酔える感じ。
ここでいいなあと思ったのは、石室?の中に閉じ込められたなつこさんが、救い出しに来た主人公に対して「大嫌い!」と叫ぶ場面。
式紙達(?)からの攻撃を受けながら、主人公は初めてなつこさんに対して「おかあさん!、なつこおかあさん!」と返す。
単純に相手が好きだとか、すっかり全てを受け入れて、とかじゃなく、いろんな気持ちが絡み合う中で、互いを確かめ合っていくような、大事なとき、大事なタイミングで、それを行っていく。そして乗り越えていく。
そんな場面。
心を閉じたままでは、前に進めない。
主人公は、ここでなつこさんを母として受け入れる決断を、自らに下している。
唐突で主人公の気持ちが分からないという人もいると思うのだけど、たぶん、主人公自身も何でなのかとか考えて分かってやってるわけではないのだ。その瞬間に、こうしたい、こうしないといけない、今すぐじゃないといけない!という思いが、あの場面を作った。
そういうリアリティが、あの場面にはある。この場面を観れただけで僕は、元は取った、と思った。
じつは、この文面を作る数日前に「コクリコ坂から」を初めて観た。家族がテレビ放映を録画しておいたんだけど、そのままになっていたのだ。
期待してなかったんだけど、心の描写は、ちょっと感心した。
心理的にどうとか、台本がどうかとか、そういうのではない。
こういう言い方はあれだが、普段のくらしの中で人は「完璧な台詞」を言えるものではない。「完璧な演技」も出来ない。まあ、映画のようにはいかないのだ。ぎこちなかったりズレたりする中で、試行錯誤しながら気持ちを通わせていくものだ。
そういう「努力」をしているのが垣間見られる、そういう描き方が成されている。微妙にぎこちなかったり、逆に思い切りが良かったり、何考えてるのか不明だったり。
そうなるのが本来、自然であり、そうでないと本当は、人を取り巻く世界は動いていかない。
これは、最新作の表現にも引き継がれている、と感じた。
駿の描き方なんだろうか。どこまで意図的なのか。そこは、よく分からないのだけど。
20日、追記。
なんと、コクリコ坂は駿ではなく、吾朗監督だそうだ。適当にやってるからこういうポカをやらかすのである。
駿は脚本で、監督は吾朗だ。
しかし実際のとこ、石室のシーン以外はいつもの駿だと思う。あそこだけ、なんだか異質なのだ。それに驚いたというのがある。
31日、思い出したので追記。いつもの駿じゃないシーン。
まず、オープニング。火事の中を主人公が病院に走るシーン。駿にしてはシャープすぎる。いい意味で。この数分間が凄すぎた。
次、なつこさんが弓を射て主人公を守るシーン。あと、主人公が青鷺の羽根で作る矢の飛び方。ここら辺りはかっこよすぎる。
そんな感じで、いい意味で驚かされる場面がある。
それにしても、なつこさんが弓を射るシーンは謎だ。
物の怪と対峙できる女性として描かれていて、おなかに子を宿して戦う人になるのかいな、と思ってたら違う方向に行った。
だけど、既にあの時点で半分異界に足を突っ込んだ人なのだ。いつから突っ込んでるのだろう、とか。
9月22日、追記。
他のサイトのレビューで、あの場面は真人(主人公)の夢だ、という説明があった。
言われてみると、なるほど、だ。
そう受け取る方が、あのエピソードを理解しやすくなるように思う。
実際、そのあと真人の看護をしに来たおばあさんが「夢でも見たんでしょう」みたいなことを言っていたと思う。
9月25日、追記。
あれが夢だとしたら、真人となつこさんは、たぶん、共に病床の中で、同じ夢を見たのだ。
終盤、ひみちゃんと鷺男と主人公の活躍。
やっぱり画面は美しく、そこに溢れるマンガチックなインコたち。なんでこんな、マンガなんだろうね。そういう描き方される理由もあるのだろう。まあ、リアルタッチだったらマジ怖いしな。
僕は気付かなかったんだけど、ひみちゃんは主人公になつこさんのことを「妹」と言ってるらしい。一緒に観に行った家族がそういうのだ。だから、主人公はひみちゃんは実母と知っていると。
えぇぇ、そうかあ?、、、
僕は気付かなかった。だから、主人公は知らないままに現実に帰ったのだと思っていた。どうなんだろうか。知ってたら、話の展開が違ってくると思うのだけど。
これは、そのうち2回目観るときに確かめようと思っている。
主人公が、大伯父から異世界を引き継ぐよう言われて断る場面、淡々と描かれて、全くドラマティックじゃないんだね。大伯父も、ああ、そうかい、という感じで受け入れて。
インコが暴れて世界がガラガラ崩れて、周りはドラマティックなんだけど、ひみちゃんも主人公も、思いは定まっててゴールを目指すだけなので、そういう意味では、淡々としたエンディングだと思う。
観てるこっちは、いまいち盛り上がらないというか。勝手にやってるなあって、置いてけぼりというか。
崩壊と帰郷という意味では、ラピュタとかもそうだけど。いや、他の駿の作品でもそういう構造があるのはあるのかな。
しかし、何というのか分からないが、僕は、静かな崩壊だなと感じていた。
その世界の中での大事。
そんなことより、主人公にとって大事なのは、帰ってからの世界なのだ。
なんというか、駿から「さあ終わりだ、帰った帰った」と言われてるような、そういう終盤だったような。鳥の糞まみれな画面についての解釈は、まあ、あまりにも印象が強いので、ここでは敢てしない。
映画作品そのもの自体以外から観客に与えられる情報が少なく、映画自体は描きたいものの詰め込みで、一見、とっちらかっている、かのように見える。しかし、そういう見え方でも、ちゃんと考えて並べられているんだろうと思う、たぶん。
でも、考えすぎても意味ないんじゃないのかなあ、という気がする。それが僕の観終わってからの感想だ。美味しい料理の皿はいっぱい並べられている。どこからとって食べてもいい、バイキング形式というか。そういう観かたをしてもいいんだろうなと思う。
最後の、穏やかな日常の画面がきれいで良かったと思う。
20世紀のアングラファンタジー映画はそういう終わり方が多かった気がする。
最近は、ああいう映画はどこかで作られているんだろうか。
21世紀は、あんな牧歌的な世界観は、現実に押しつぶされてしまったような気がする。
でも人の営みは変わらない。押し流されそうなときでも、いや、ときにこそかな、忘れずにいられたら、ということがあるだろうと。
こんなレビュー(?)を挙げるのは僕としては珍しいのでどうしようかと思ったが、アングラ映画に対しては、レビューを捻ったりするのが似つかわしいと思うので。
まあ、そんな感じだ。1回観ただけじゃ分からないね。
8月も終わるので、ネタバレ追記。
つうか、僕が思いついたことだけど。
タイトル、なんでこれなんだというか。
主人公が異世界から持ち帰った「石」、青鷺が「御守になる」と言った、あの石こそが「君たちはどう生きるか」なのだ。
つまり、亡き母が託した、主人公が泣いた、あの本だ。
あれが御守りになって、主人公を守った。
たぶん主人公は、年を重ねるに連れて、本の内容を忘れていくだろう。でもその本を読んだことで、自分の心、魂が守られたことは、心の奥底に残るのだ。どんなにその本が大事だったかを、すっかり忘れたとしても。
そう、「作品」は「御守」だ。
駿は、観た人の御守りになる作品を、後に忘れ去られたとしても、その時はその人を何かから守る御守りになれる作品を、作りたいと願ったのだろうと、僕は勝手に思う。
この作品のタイトルに「君たちはどう生きるか」を持ってきたのは、2つの意味がある。
ひとつは、若い後輩へのメッセージ。どういう気持ちでクリエイトしていくんだい?という問いかけ。
これは分かりやすい。
もうひとつは、作品の中で数分しか出てこないこの本の存在が、実は重要なんだということを明示するためだ。
作品に触れることが人に何をもたらすかを序盤に示し、更に主人公が「異世界から現実に持ち帰る御守」という形で示し、それが、いずれ忘れられていく運命であること、そして、それでいいのだということを示した。
駿は、そういうことこそが大事なのだと示したのだと思う。
さて、話変わるけど、
そうなると13個の石というのが駿の作品だと言われているが、実際どうなのか、と思ったり。
まあ、そういう解釈もありだ。でも、大叔父は駿とは関係ない、ただの作中のキャラクターだと解釈したら、たぶん大叔父の頭の中にある、あの異世界の元ネタが13個あるよ、という意味なのだ。
ほんとかな?w。
まあ、こんなとこかな。
Jan 01, 2023
謹賀新年
あけましておめでとうございます。
いろいろありますが皆様のご健康、ご健勝をお祈りし、今年がより良い年でありますように願っております。
更新は滞っていますが、無理ない範囲で運用してまいりますので何卒よろしくお願いいたします。
そんな感じで、新年の挨拶をこのサイト上でしたことが、今まであんまりない。
昔は書いたこともあったが、なんだかいつの間にか、書かなくなった。ツイッターでも明けおめとか、あんまり書かない。
しかし、なんとなく今年は挨拶ぐらいは書いておくことにした。
そんな感じなので内容はない。
ここ数年、世の中コロナで大変だけど、昨年は輪をかけて大変だった。世の中があれやこれやとありすぎて、気持ちが落ち着かないというのも困った。
日本国内も世界情勢も、どうなるのかまったく先が見えない。そんな中で、コロナ対策は毎日が気が抜けない。昨年の秋以降、僕の職場ではコロナクラスターを生じていないということが殆ど無くなった。あっちで収まったと思ったらこっちで発生するというのを繰り返して、コロナ対策担当の職員はそっちにかかりっきりだ。コロナ対策班っていっても、元々それだけやってる職員じゃなくて、やるべき日常業務、役職は別にあるのに選出されてやってるので、開いた穴は他の慣れない職員が肩代わりしているのだ。そんな中で、家族が発症し濃厚接触者になるとかで仕事を休む者もいる。そのような状況が続いていて、みんなの負担が増している。
それでも、まあ、やるしかないということだ。僕などは三が日休めるんだから感謝である。
そんなこんななんだけど、気がついたんだけど、僕がサイト運用し始めて今年の2月で20年になる。
20年といえば、昔だったら成人式だ。
愚痴みたいなことを書いたりするけど、よくまあ、飽きずに続いているものである。
最初はコピーコントロールCD反対のサイトを作ろうと思いたち、わけがわからないので契約しているプロバイダのサービスを借りたのだった。それ以降、契約継続しながら今に至っている。
昨今はCCCDどころか、CD自体が少なくなった。時代は変わる。音楽の有り様を憂うとか、そんな呑気なことは言っていられない時代になりそうだ。
そうはいっても、継続は力なりといわれる。ぼちぼち続けていくつもり。
みなさま、風邪など召されぬように。
Oct 23, 2022
3ヶ月も空いたので近況報告だけど、大したことは何も書いてない
すっかりブログ更新が滞っている。
世の中はほんとうに大変だ。
3年前から続くコロナ。今年2月からわけわからん戦争が始まった。
職業柄もあり生活防衛もありコロナの情報は追わなくてはならない。ウクライナの戦争も世界の向かう方向を知らないわけにはいかないので追いかけることになる。
それでもまだ、6月までは余裕があった。
7月、朝鮮半島に拠点を持つ世界平和統一家庭連合(元統一教会。莫大な献金を日本の信者から強制的と言っていい手法で集め、社会問題化している。その金は北朝鮮に流れSLBM開発の一助になったとか、、、)が、日本の政治、特に自民党に何かしらの影響を与えていたということが白日の下に晒された。
何かしらの影響って、ひとことで済ますには規模が大きすぎる。
国政だけではなく地方行政や草の根の活動まで、あちこちに知らない間に浸透され、教育やLGBTなどの方向性に対して人々が気付かないうちに影響を与え、諸外国の右傾化にも日本から巻き上げた金を以って影響を与えていることが、この3ヶ月で広く知られることになった。
これは、全日本国民にとって課題であり、黒歴史且つ将来への禍根そのものであって、知らないでは済まされない。何が起きているかを追いかけないわけにいかない。
2024.06.11.追記。
さて、統一教会の影響については、2年前は随分心配したが、その後、自分なりの拙い情報収集で、まあ、他にもっと問題がある団体は歴史的に脈々とあるのを知って、さらに最近は自民党自体が政権担当能力すらも所謂「終わってる」集団だということが世間的にもはっきりしてきたので、いよいよ闇は深いけど、さあこれからどうなるのかな、という感じだ。要するに統一教会なんてまだ小物で、自民党自体があれなので根っこから植え変える時期が来たのだろうということで、今更追記しておく。
そんなわけで、ブログ更新する暇はなくなった。
趣味のオーディオは、BGMで音楽を鳴らす以外はしていない。
手がかかることは出来なくなった。後回しである。
音源のアップサンプリングをどうしたらいいのかというのは大きな課題なのだが、ある程度落ち着くまでは取り掛かれそうにない。なにしろ、試聴に使う音源の選定すら出来ていないのだ。
以上、近況報告まで。
アップ5分後に追記。
うちの職場では現在4回目のクラスタ発生で、ちょっとバタバタしている。
コロナは早く終わっていただきたいのだけど、あと数年以上続くという予測もある。幸い、オミクロンは重症化は少ない。気を付けながらウィズコロナだ。
Sep 25, 2020
音楽を聴くにはどうしたらいいのだろうか
今回のエントリーは、音楽とどう向き合うか、という話だ。
オーディオも関係してくるけど、たいした内容はない。
他人にはどうでもいい話だ。
僕は中学の頃からラジオでポップミュージックを聴き始めた。
高校でビートルズに嵌ってプログレ、レッドゼッペリン、パンク、大学に入った頃にインディーズブームがあり、それからは最新のポップミュージックをずっと追いかけていた。
オーディオセットがましになってからは、クラシックやジャズなども聴いていたけど、メインの音源はロックなどポップミュージックだった。
それが、あの311以降、がらっと変わってしまった。
新しいポップミュージックを聴かなくなったのだ。
昔から追いかけているミュージシャンの作品は入手するが、新人はほとんど聴かなくなった。
この心境、志向の変化は、うまく説明できなかった。
災害当初は、新しい音楽なんか聞いていられるかという気持ちだった。それならば分からなくもなく、そのうち聴く気になるかなあ、などと思っていたんだけど、その後、年月が過ぎても、聴く気になれない。
では、手持ちの音源ばかり聴いていたのかというと全くそんなことはなく、主に新たに入手した音源を聴いていた。
クラシックの比率は大幅に増えた(これはオーディオシステム上流の改善に牽引されたと思う)。ポップミュージックは、聴いたことがなかった過去のミュージシャンが中心で、特に多かったのは安価なCDボックスセットで販売されているものだ。
つまり、クラシックが増えたとはいえ、ポップミュージックもあれやこれやと聴いてはいたのだ。逆に最先端中心に追いかけていた頃より、幅が広がったかもしれない。
10年経っても、最新のポップミュージックは聴く気になれなかった。
飽きたんだろうか。
年をとって付いていけなくなった?
なんというか、聴いたら面白いと思う瞬間はあるんだけど、なかなか追いかける気になれないのだ。
じゃあ、ストリーミングで十分じゃない?
、、、、、、
ここ数年、ストリーミングが音楽配信の主流になったと言われている。そこそこ良好な音質で聴ける環境も整ってきているらしい。
CDは古いのだそうだ。
新しい音源は、ストリーミングじゃないと聴けなくなるのかもしれない。
最近聴いているのはクラシックが多いけど、クラシックだって多分そうなるんだよ?ひと月に千円とかなら安いじゃないか。だいたいCD置く場所、なくなってるじゃないの。
しかし、だ。
そういう理屈は分かるけど。
全くそっちに行く気になれなかった。
今回、Amazon Prime Musicがある程度まともに鳴るようにセッティングしてみようと思ったのは、僕にとってストリーミングがどういう位置付けになるのか、試してみないことには分からないと思ったからだ。
やる気が起きないからと手を付けなかったら、たぶんずっとこのままだ。
HDとかUnlimitedとか、高音質や曲数が多いのもあるけど、無料で試せるのは短期間で、とてもじゃないけど見極められない。
そんなわけで、まずはPrimeで良かろうと割り切って手を付けてみた。
曲数なんて大して問題にならないだろう。ストリーミングは最先端ばかりではない。古くてCD入手困難な音源がしれっとおいてあったりもする。もちろん無い音源も多いけど、聴いたことがない音源には困らない程度の量はある。
だが、そんなにあれこれ聴こうという気に、自分はなるのだろうか。
昔は、とにかく広く浅く大量の音源を聴こうとしていた。聴いたことがない音楽があるということ自体が聴く理由だった。
何時頃からか、そんな無闇なやり方とは折り合いをつけて、今はずいぶん様変わりして物理的時間的限界で量を聴けなくたって別に困らない。
そうはいっても、興味がある音源があれば入手しようとするのだけど。
最近は何に興味が?
改めて考えてみたら、、、気が付けば、高音質音源だ。
先日、アンプが故障して痛感したことがある。
僕は良い音で鳴ってるオーディオがないと、もたないようだ。
短期間なら音が良くなくてもいいが、長くなると息が切れたような気分になってくる。不足感が半端ない。そしてたぶん、音が悪いなら聴かない方がマシだ、というようなことに、最終的にはなりそうな気がしたのだ。
高音質な音源は、鳴ってるだけでも気持ちがいい。癒される。どういうんだろうね、まるでドラッグ、依存症だ。
昔、僕にとって、世界と音楽は重なり合って存在するものだった。いや、音楽は世界につながるためのプラグの一つだった、というべきか。世界を音楽で彩ることで、僕は世界の中で息をしていた。
それが、最近そういう感覚がない。
311以降、世界と音楽は、僕の中で切れてしまった。
僕自身が、切ってしまったのかもしれない。
あの数年後、僕はツイッターに「伝説を語ることが空々しく感じられるけど、歴史に触れることには逆にリアリティがあるような気がする」とツイートしている。そんな感じで過去のポップミュージックばかり聴いていたんだね。
そして、切れたままなのだ。
僕から見える世界は、この10年で、ずいぶん変わってしまったと思う。こんな世界を彩ることが出来る音楽を、僕は見つけられなくなったのかもしれない。
まあ、それでも息をしていられるようになったということだけど。
だから別にそれでいけないことはない、とも思う。
昔の僕にとって音楽は空気や水のようなものだったが、今の僕にとってはドラッグだということだ。はたから見たらやってることはほとんど同じで、見分けがつかないだろう。
それが僕にとって問題なのかといえば、大した問題ではないっちゃないので、別にいいっちゃいいんだけど。
それとは別に。
音質希求の方向性は、オーディオシステムに影響する。
何が言いたいのかというと、つまり、ストリーミングは現状、768kHzにアップサンプリングできないのだ。
ストリーミング音源ではそれが出来ない。
僕にそのスキルがない。
そうした音源が主流になっていくとき、どう僕の中に位置づけるのかということになる。
昔は今ほど音質は大きな要素ではなかった。
今はそうではない。
ふだん、パソコンで音源を鳴らして平気でいたりすることもある。カーオーディオは現状の音質で全く不満がない。
しかしそれは、メインに高音質なオーディオがあるからこそ一時的に我慢できるのであって、それがなくてパソコンでしか聴けなかったら、車でしか聴けなかったら、、、
僕は聴くのをやめるだろうか、それとも、聴き続けるだろうか。
聴き続けるとしたら、何を聴くだろう。
それは世界を彩ることができる音楽なのか。それとも、もっと違う聴き方になるのか。
Prime MusicをPulseaudioで鳴らしてみようなどというのは、そういう疑問に対する一種の足掻きということだ。
そんなこんなで、うちでもストリーミングの利用が本格化?しつつある。今回のエントリーは一種の定点観測記録のようなものだ。
次回は、ストリーミング自体について、オーディオ中心の話になる。
いや、、、思った以上に、ストリーミングって、オーディオ的にも面白いね。
May 05, 2018
子供と2人で遊ぶトランプゲームを創作したよ
準備
用意するのはトランプ1セットと、カードを広げる場所。プレーヤー2人。
カードからジョーカーを抜いて、赤黒の山26枚ずつに分ける。
プレーヤーは赤黒を決めて自分のカードの山を取る。各々26枚のカードをよく切り、裏にして2枚ずつ13の組に分け、前に並べる。

ゲーム開始
プレーヤーは13の組から戦いに出す組を選び、真ん中に出す。

戦いのルールは簡単。カードをめくり数字が小さいほうが勝ち。
まず双方、1枚目のカードをめくり表にする。

カードの数字を比べ、勝ったカードはそのまま残る。
負けたプレーヤーは負けたカードを流す。数字が同じなら相打ちで双方ともに流す。
1枚目のカードを流したプレーヤーは、残っている2枚目のカードをめくる。
数字が小さいほうが勝ち。負けたり相打ちになったカードは流す。

残ったカードは、勝ち残ったカード、裏返しのまま残ったカード、ともにプレーヤーの点数になる。
プレーヤーのもとに戻し表にして並べておく。

13組の山でこの流れを繰り返す。

勝敗
13組全ての戦いが終わったら点数を集計。カードの数字がそのまま点数になる。
点数が多いプレーヤーが勝ち。
こんな感じ。
13組は多すぎということなら、ハートとスペードを使って2枚6組と最後1枚で勝負するとかもありかな。計算しにくいので絵札は10点でもいい。
あんまり頭を使わずにプレーできるけど、子供はそこが不満な様子だ。
たいていゴールデンウィークの祝日には仕事が入るのが常だったんだけど、今年は珍しく日曜祝日が全部休みになっている。
うちの子供はオリジナルのゲームを創作するのが好きで、でも大抵はルールがわけが分からなくなって完成しない。だけど今回は親が関わることになって、珍しくそれなりに遊べそうな形になったのでアップしてみた。
ゲームに名前が要るんだけど、提案した案は全て子供に却下された。
しょうがないので名無しのままだ。
Dec 21, 2017
「おんな城主 直虎」が最終回を迎えたり
おかげさまで1年間、楽しませていただきました。
放送中は視聴率が振るわないとか下らない理由で内容のない意味不明なレビュー記事がビジネスニュースのサイトとかに書かれたりしていたけど、今となっては過去の事とされているようだ。練りこまれた台本、台詞回しの凄さ、それに付いて行く役者の演技に魂がこもっていること、などなど、あちこちで今更のように語られている。
しかし、僕なりに感じた直虎の他では見られない魅力というか深淵というのか、この場で書いておこうと思う。
僕は不勉強なので、ありふれた内容の文面かもしれない。予めまとめると、直虎というドラマは異界と隣り合わせの現世を描き切ったことで成功したということを書いている。
どこから手を付けたらいいか。
だらだら書いていく。
この10年以上、僕にはTVドラマを見るという習慣がなかった。
今年の大河、女房子供に付き合う形で見ることになった。女房は歴史オタクで大河にはうるさい。女大河はいまいちなのが多い、「戦さはいやじゃ!」とか言って押し切るからリアリティがない、などと聞かされながら見始めた。
しかし、いきなり僕はオープニングタイトルにもっていかれてしまったのだ。
見てるうちに、不覚にも涙が出てしまった。
そんなドラマ体験は今までないよ。
もしもドラマの内容がダメでもオープニングタイトルだけ1年見てもいいかもな、などと考えた。
それだけ考えて作りこんだ映像、音楽だったと思うし、直虎というドラマの主題がとても上手く表現されていて、長いタイトルにもかかわらず中弛みなく最後まで見てしまう。ドラマ本編で何が語られるのか、オープニングで視聴者にも感じ取れる、いいオープニングタイトルだと思う。
次に、子役かな。
子役が子供の頃の役をするなんて当たり前のことじゃないかと僕なんかは思ってたけど、最近はあまり重視されてなかったらしい。子供時代がきちんと描かれ、しかもこの子役が馬に乗ったり(!)、坊主になったり(!!)する。
このドラマは本気らしい、という気分にさせられる。
ちょっと、こっちも本気で見ないといけないかなというモードにさせられていくのだった。
その子供時代に、竜宮小僧なる謎の言葉が出てくる。あと、井戸が。
異界につながるような井戸が。
この井戸のそばで、登場人物たちは胸の内を語り、ドラマの行く末が決まっていく。異界への窓がぽっかり開いている村では、坊主たちが頻繁に行き来し、主人公もまた尼になっているのだ。そして度々、登場人物たちが井戸端で死者を思い酒を飲んでいる。
このドラマでは、異界の傍に人間界があるということが最初から構造化されているのだ。
最初はそのことには気付かない。
あまりにも自然に、そこにあるので。
しかしドラマの中、そこかしこに、ちらりちらりとそれが異物として顔を出す。
台本は、歴史考証はしっかり踏まえながら新たな解釈を盛り込んでおり役柄の心理描写もすばらしくリアリティがあるのだけど、そこかしこに顔を出す異界からの使者、信号は、このドラマに独特の奥行き、ゆらぎを生み出している。
例えば、徳政令の回。
驚かされたのは亀が演技をしたことだ。
神社で直虎が徳政を受け入れ花押を書こうとしたところ、亀がどこからともなく現れて止めるのである。
見ていたこっちは、これは凄い話だと思った。
そもそも、亀が出てくる必要性は筋書き上はないのだ。直虎本人が1人で決心しても筋書き上は問題ないのだ。でも、でも、亀が止めるのだ。
直虎というドラマでは、亀が直虎を止めることに意味がある。
今から思えば、この展開を受け入れられるかどうかで、たぶん視聴者の篩い分けが成されたのだ。亀を受け入れることで、視聴者はこのドラマの魔法に絡め取られたのだと思う。
最初、僕はそれを「中世らしい感覚」なのだと思っていた。戦国の世を生きる登場人物たちの心理が、当時の宗教観世界観も含めてうまく脚本化されているから、現代人の感覚とは違う死生観、人生観が表現されてドラマにリアリティを与えているのだと。
でも、毎週見続けるうちに、どうもそれだけじゃないと感じ始めた。
心理描写、戦国社会の描写とは別に、彼らを取り巻く世界の表現が、現代的なリアリティから逸脱しているのだ。前述の亀の件もそうだし、空に龍雲が現れたり、信玄を寿桂尼が呪い殺したり、離れているのに同じ手筋で碁を打っていたり。そして、死者から遺されたものが生ける者を動かす力を持つ。
アレルギーに対する減感作療法のように、少しずつ視聴者のガードが崩されていく。
これを「中世らしい感覚」と言って良いのか分からない。
当時は祈りや呪い、迷信が現代よりもずっと深く意味を持っていた時代。世界の成り立ちも、現代とは違っていたんだろうか。点在する目に見えるエピソードと、通奏低音のような何か、それは竜宮小僧の存在感かもしれないし、積み重なる死者たちへの思いかもしれないし、心のうちを隠さなくては生きていけなかった人たちの心の声の行き場なのか。そうした不思議な世界が、こっそりと、しかし実在感を持って描き出されている。
迷信を信じてしまう心性は現代を生きる僕らの心の底にも息づいている。直虎を見ていると、なんというか、それが蠕き始めるような、そんな感覚があるのだ。
その結果、視聴者はどうなるか。直虎が政次を槍で刺すのを受け入れるようになるのだ。
そう、あの名場面、かなり話題になったあの場面。
しかし、考えてもみなよ。
最終回終わって一息ついて覚めた頭でもう一回考えてみようよ。
あんな、とんでもない話ってあるか?
直虎が、政次を刺し殺しちゃうんだよ?
ほんとにあれって究極の信頼関係って涙したりして、本当にそれでいいの???、、、
僕は思うのだけど、あれが通用したのは、視聴者が受け入れることが出来たのは、直虎の舞台が異界とつながった世界、現代人の感覚から外れた世界だということを、みんなが心の奥底で受け入れることができていたからだと思うのだ。
このドラマは、意識してかどうかは分からないけど、そういう構造の下、従来の大河ドラマが絡め取られてきた現代人のリアリティ感覚という縛りを、無化することに成功したと思う。
というか、直虎の世界で通用するリアリティを獲得したというか。
政次ロスが通用する世界観を予め構築できていなければ、あんな場面、絶対に視聴者に受け入れられなかったはずだ。それがこのたび、制作者も視聴者も、これだよね!って感じで受け入れ演じて観てしまった。
あの場面はまるで、神話の世界のイコンか何かが現れたかのようだった。
そして、その流れに乗ったまま、最終回を迎えたわけで。
最終回では、直虎の死に際して、笛が万千代のもとから直虎のところまで飛んでいく。
笛の音を聞いた直虎は子供に戻って願いがかなう未来を見に行く。
最後のシーン、直虎が死後の世界で過ごしている場面でドラマは終わる。
異界、死後の世界が現世の傍にあるという世界観を、あからさまに表現した、そんなファンタジックな展開が全く不自然じゃなくて、むしろ感動的な必然に感じられて、すばらしい最終回だったと思う。
直虎は、制作側と視聴者側ともに、独自の世界に巻き込むことに成功した。
おそらく、これは直虎を主人公に選んだから可能だったんだろうと思う。
半身を異界にかけたような存在でいながら、大河ドラマの主人公を張ることが出来る歴史上の人物は、なかなかない。史実となる資料がほとんどない直虎だから逆に、リアルでありながらファンタジックな実在感を描き出すことが出来たんだろうと思う。
史実が多い人物はファンタジックにできない。下手したら荒唐無稽になってしまうからだ。
そういう意味で、直虎を超える大河ドラマを作るのはかなり難しいはずで、唯一無二となるかもしれない大河を最初から最後まで楽しめた僕は幸運だった。ドラマという異世界で1年間遊ぶことが出来た。単に良く出来たドラマを見たという以上の、不思議な感覚を楽しむことが出来た。
22日、今更分かりやすい言い方を思いついたので追記。
直虎に関わった者はみんな、製作側も視聴者も、竜宮小僧の手の上で遊んだのだ。
徳政令の回、竜宮小僧は亀になった。
その後、竜宮小僧の影は薄くなったかに見えたが、それは竜宮小僧が亀となり直虎宇宙の底を支えたからだ。
ほら、インドの言い伝えでは宇宙の底に亀がいるでしょう。
そういうことなんだ。
年末年始には総集編があるらしい。
http://www.nhk.or.jp/naotora/info/program/article51.html
こんな濃厚なドラマ、半日で尺が足りるんだろうか。どう料理されてるか楽しみだ。
Aug 02, 2016
ドメインをロストした
私が悪いんです。
繰り返し来ていた契約継続確認のメールを放置していたのだから。バカである。
例年、放置してたら継続だったのが、今年は管理会社が変わってて手続きが必要だったというわけ。
しょうがないので、新しいドメイン契約の手続きをして、tikitikiに連絡をして数日待って、新しいドメインということだ。以前取ろうと思って取れなかった.netドメインだけど、こういう経緯で取ることになるとは。
せっかくの機会だからと気を取り直して、エントリーの日付けが狂いまくっていたのを直した。時刻までは正確に直せないけど、日付だけでもだいぶマシだ。エポック秒(UNIX時間)をまとめて管理しているdatファイルを修正。半日かかった。こういうことでもないと直せない。
ついでにいくつかカテゴリ分類が違うのではないかと思われるエントリーを移動した。
ブログタイトルをabk1's scratched blog 3にした。ipアドレスは同じだけど、ドメインが変わっちゃったからしかたない。
もうこんなことはないようにしたい。
Oct 23, 2009
Sep 12, 2009
technobahnの日本語ページがなくなった
technobahnは面白い科学ニュースサイトで、ときどき見に行ってたんですが(ちょっと訳が微妙なこともあったようですが)、日本語対応を止めたようで、残念です。
トップの下の方に「Sayonara Japan」とリンクがあります。
リンク先のダンボのムービーがいい。音源にI Leaving on a Jet Planeが使われています。