Current filter: »FileAudio« (Click tag to exclude it or click a conjunction to switch them.)
Jul 05, 2017
オーディオ状況報告(2017.07.05.)
現在のオーディオシステムについて記録。前回が11月なので半年以上たっている。
前回、LibreOfficeのドロー機能で作った図はHDDが飛ぶのと同時に消えたので、また作り直した。
今度こそ1回作っておけばあとは楽だろう。
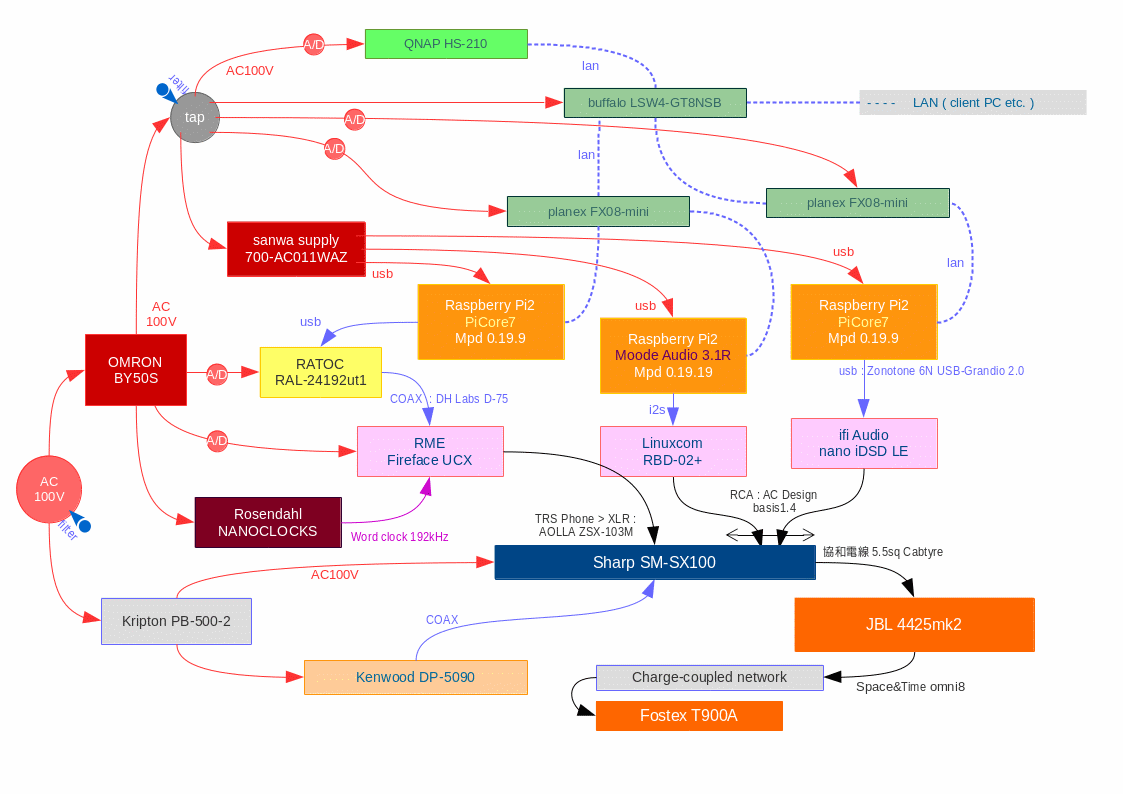
変化したところを見ていく。
まず、タコ足配線のテーブルタップに「filter」が刺さっている。
これはAC100Vにも刺さっていて、コンデンサーを使った自作ノイズフィルターといったところ。
参考にしたのは以下のリンク。
VGP2007SUMMERを受賞した電源ノイズリダクション製品「Noise Harvester」を福田雅光氏が体験
http://www.phileweb.com/news/audio/200706/22/7306.html
画像
http://www.phileweb.com/news/audio/image.php?id=7306&row=2
Noise Harvesterは簡単な回路図が公開されていて、どうやらコンデンサーだけで効かしてるらしい。
他にはこれも参考にした。
のんとろっぽ audio TIPs まずは、安井式電源フィルターのお話
http://nontroppo2010.web.fc2.com/etc_tips.htm
安井式電源フィルターはコンデンサ、コイル、抵抗による簡単なフィルター。
これらの記事を参考に、簡単すぎて恥ずかしいようなものをタップと壁コンセントに刺している。
しかし、これが意外なほどの音質改善効果があった。
特に効いたのは、SM-SX100のCOAX入力。つまりCDプレーヤーDP-5090の音が大きく改善したのだ。昔からSM-SX100のデジタル入力はよくないと言われていたんだけど、これなら充分使えるという感じになった。
今は子供が主に使っているんだけど、傍から聴いていて良くなったのがはっきり分かった。
あと、FX08-miniの配置が多少変わっている。直列じゃなく並列なのはあちこちに動かしているうちに結果としてこうなったから。図のA/Dの丸いマークはACアダプターを表している。
2つのFX08-miniは、かたや以前からある装置に、かたや新規のDAC、ifi nano iDSD LEに繋がっていく。
さて、一応メインのデジタルトラポはRaspberry Pi2が3つ。全部、mpdが動いている。そのうち2つが「384/24」にアップサンプリングの設定。
半年前は192kHzだったので倍になった。
Hifiberry Digi+はお蔵入りに。
192kHzのPi2はfireface UCXに繋がっている。それがUCXの上限だからだ。
Moode AudioにlibsamplerateをインストールしCD音源を384kHz出力にアップサンプリングしてi2s DACで聴き始めてから、こっちの方向性で動いている。
なにしろCD音源から簡単に高音質が得られる。
天上のオルガンのような300kHz以上のハイレゾ音源には及ばないけど、かなり迫ることが出来る。
僕はCD音源が多いので助かるのだ。
nano iDSD LEは安いDACで取り急ぎ実験に必要ということで購入したけど、最近のDACの進歩はとても速いと感じさせられた。今後、上流をどう組んでいくか考えないといけない。
192kHzのfireface UCXと、384kHzのnano iDSD LE、両者の比較は出来ていない。
まあ、そのうちしようと思うけど、ともにメモリ再生なので、手軽に聴けるMoode + i2sDACに使用機会を奪われている。
この2台はRCAケーブルのbasis1.4を分け合っていて、どちらかを使用するときにはケーブルを継ぎかえるようになっている。アンプのRCA入力端子2組のうち1組が使えないので、そういう使い方になっている。
書き忘れていたけど、piCore7はメモリ再生でusb出力。Moode AudioはNASマウントでi2s出力で使用している。
NASの手軽さでメモリ再生の音が出たら本当にありがたいんだけど。
あとは、VRDS-25xsが外れた。トレイが動かなくなった。物置にしまってあって、修理したいと思ってるけど手が回らない。どうやって修理するのか調べるところからやらないといけない。
正直、復帰は難しいかなと思うけど、捨てる気にはなれないので当分はしまっておくつもり。
長いことありがとう、お疲れさまという感じ。
Oct 06, 2010
4年前との違い
前回、久しぶりにオーディオ関連のエントリーを上げました。
なんとなく、当サイトの過去の記録を読みかえしました。
当時はブログエントリーじゃなかった。
2006 02.05. iTunes & AirMacExpress
AirMac Expressの音について、ちょっと気になったことが。
引用。
Lossless、AIFFよりもCDプレーヤーからの方が音がいいというのは、かなり僅差です。
ブラインドでは区別がつきません。
自分で書いた事ながら、かなり意外。
ブラインドで区別がつかない?
現在はそうは思いません。
前回のエントリーで「VRDS25xsで再生するCDの音質は、AME経由より数段よろしい。」と書いています。
個人的表現ですが「数段良い」というのはブラインドで区別が付かないとは言えない。
ブラインドで違いが分かるどころか、はっきりどっちがいいか分かるレベルだと感じていました。
この4年で何が違ったのか。
1.マックが変わった。
Powerbook G4 alからMacbook Proへの変更。
そしてiTunesのアップデート。2006年にはv6、2010年現在v9.2.1。
iTunesのバージョンによって音質が違うという話を聞いた事があります。僕には何とも言えません。
しかし、重いソフトが音楽再生の負担になる可能性はあると思っています。
それは後述の経験によるものですが。
しかし、これは今のほうがAMEの音が悪い理由にはなりません。
2.接続方法が変わった。
2006年の記録によると、当時は無線LANで接続してたんですね。
しかし実はその後、再生が途切れる、音質悪化などの理由で、有線LAN接続に変更しています。
詳しくは以下にリンク。
Apple Discussions - Japan: 曲が再生中に止まるケース
上記のディスカッションにflyingnote名で参加してます。
というか、ほぼ一方的に自分が報告上げてるわけですが。
2008のことだったんですね。当時のiTunesはv7。
当時、あれこれやった結果、音楽デジタル信号の伝送というのは想像以上にデリケートで、その良し悪しが音質を大きく左右するということが分かりました。
環境が悪い場合、再生音が途切れたり、途切れないまでも酷く音色が変わったりします。
リンク先から引用しておきます。
結局、何が一番効いたのかはよく分かりません。
試みたのは、
1)電波干渉の制御を使用
2)AirMac Expressの無線機能の停止、他の無線端末への接続
3)チャンネルの変更
4)ipアドレスの変更
5)スイッチングハブの追加
6)ファームウェアのアップデート
2は効果がありましたが、効果が持続せずやめています。
4は効果がないと判断しました。
1、3、5、6は改善があったように思いました。
何が一番効果的だったかは、よく分かりませんが、良好に再生するにはネットワークが安定していることが重要だということだけはよく分かりました。
コリジョンについて「通信用語の基礎知識」というサイトにリンクします。
http://www.wdic.org/w/WDIC/コリジョン
http://www.wdic.org/w/WDIC/無線LAN
これらの説明を読むに、IEEE 802.11系の無線LANは半二重通信なのでコリジョンを生じうる、ということになります。
当方で起きている再生の中断がコリジョンによるものだとしたら、iTunesがインストールされているPowerbookを有線LAN接続にすれば、確実な対策になる可能性がありますね。
実際、有線LANにしてから再生は安定するわ音質も良くなった気がするわで、以降は無線にすることはありませんでした。
あちこち移動できない利便性低下はありましたが。
しかし、これも今回とは関係ない。なぜAMEの音が悪くなった?
3.住居が違う。
2008年の春に引っ越したんでした。
住居環境が全く違います。
特にVRDS再生の肝「床」の状況が違う。フローリングからコンクリートの床に変わってます。
つまりAMEが悪化したんじゃなくて、VRDS25xsの音が数段改善しているということ。
これなら、すごく納得できます。
何で以前は気付かなかったんだろうという謎はありますが。
多分、音が途切れて聴くに堪えないAME無線LANで聴いてばかりで、比較以前の問題になってたんだと思います。
そのうちVRDS25xsはCDを読み込まなくなり修理に出され、戻ってからもラックに戻されず休眠していたわけでした。
VRDS25xs、メーカーにピックアップの在庫が無くなったという話があります。
もう壊れても修理できない?本当なのかな。非常に残念です。
大事に使っていこうと思っていますが、今後壊れたときに替えがないのが辛いところです。
多分、ファイル再生で代替するしかない。
Afplay、Core Audioは可能性を見せてくれました。今後の発展を期待します。
Dec 27, 2009
ザ・ビートルズBOX USBをEMI Japanから買った
なにも好き好んで国内輸入盤を買うことはないだろうに、という声もあろうけど、ともかく。
ビートルズUSBのファイルを聴いたので拙いながら報告します(ちょっと違うか?)。
1)まず再生状況。
普段は音楽ファイルをiTunes→AME→コンポで聴いている。
ハードはPowerBook G4 12"で、OXは10.4.11。iTunesはv8.2.1。iTunes→AMEは有線。
コンポは以下の通り。
DAC:birdland Audio / OdeonLite
アンプ:Sharp / SM-SX100
スピーカー:JBL / 4425mk2、Fostex / T900A
DACとAMEの間は光ケーブルで繋いでます。
2)flacはiTunesで扱えない。
そこで、XLDをダウンロード。で、ロスレスに変換(44.1kHz/24bitは不変)。
これをiTunesで鳴らそうということ。
CD音源のロスレスと比較してみたいと思うんだけど、うちのCDは旧盤でリマスターとは音自体が違う。
なんだそりゃだが、今回はそういうことだ。まぁ、何かやってみたら分かるだろう。
3)さて、聴いてみた。
リマスターの方がやや音圧が高い。コンポのボリュームで音量を合わせて比較。
それでもリマスターの方が楽音のメリハリが強く明瞭に聞こえる。リズム楽器系の音量が高い。これは旧盤とリマスター盤の違いであちこちで言われていたこと。
音質自体の方だけど、24bitなので音質がCDより上と言われている。
しかし、うちでは音色が現代的になっただけでトータルの情報量自体はそんなに増えてないのでは?と感じた。
iTunesからAMEに伝送される過程で24bitのメリットが失われた可能性もある。
技術的なことはわからないけど、「Come Together」のロスレスを比較すると、24bitが47.2MB、16bitが23.1MB。
両者の伝送をアクティビティモニター(Macのソフトでそういうツールがある)で確認すると、iTunesからAMEに送信されているデータは16bit、24bitともに110〜120KB/sで変わらない。
つまり、iTunesが24bitを16bitにコンバート(ていうのか?)してるっぽい。
うちの環境で聴く限り、24bitの恩恵はなさそう。
新しいOSやハードでは違うのか?そこは不明だけど、、、
4)mp3も聴いてみる。
細かい音色のニュアンスはロスレスには劣るけど、これで十分という人は多いだろうと思った。320kbpsともなればかなり音がいいと思う。
5)iTunes以外のソフトではどうか。
flacのメリットは出るのか?いうことで、Play v0.3をインストールし、パワーブックにイヤホンでflac、ロスレス、mp3を聴いてみたが正直、違いは分からなかった。
これじゃ、やりかた悪いだろうと思う。USBポートから出力してDACに送るとか方法はありそうだが、現状、そんなことする暇はないのだった、、、
6)国内盤を買うメリットはあるのか。
まず、日本国内盤USBに、歌詞とか解説等の追加ファイルは無い。
包装に貼られたシールに日本の取り扱いサイトへのリンクが書いている。そこにいくとflacのプレーヤーへのリンクとかが書かれています。しかし、これだけのために1万円高いのはやっぱりどうかと思う。
以上です。何かのご参考になれば。
ちなみに、うちのDAC、Odeon-Liteには入力信号のサンプルレート周波数が表示されるんですけど、OTOTOYのHQD、24/48のファイルを鳴らしても44.1と表示される。やはり、ファイルそのまま伝達されてない。
追記。タイトル修正しました。USBが抜けてた。
Oct 02, 2007
レディオヘッドきた。。。
すっかりご無沙汰して、ダウンロード違法化についてあちこち回って情報収集してたら、どうよ。
Radioheadが新アルバムをダウンロード販売開始・価格はオープン・・・(MAC REVIEW)
音楽業界の一つの時代が終わった…(what's my scene? ver.7.2)
オープンって、まじですか。
とりあえず、エントリあげるよ私ゃ。
4日、追記。シャーラタンズはフリーダウンロードだと。
シャーラタンズのニュー・アルバムは、なんと無料!2008年初頭にダウンロード配信(CDJournal.com)
なんか、大変な時代だなぁ、、。
Aug 13, 2007
廃盤以上の問題になるかも
昔、「ネット配信になったら廃盤がなくなる、在庫管理しなくてよくなるから」と、脳天気なことを書いた。
今になって、そんなことにはならないであろうことがはっきりしてきた、と思う。
サーバー上にしか「商品」が存在しないということは、配信する側、権利者の考え次第で、その商品を世界中の「棚」から下ろして権利者のデータベースにしまい込むことが可能になる。
つまり小売りという概念がないから、一旦権利者が「売らない」と決めた作品は、たちまち市場のどこにもなくなってしまう。CDやビニール盤のような物理的フォーマットの場合、希少な作品をあちこちの店舗を巡って探し出すとか中古品から掘り出すなどという入手方法が通用するけど、ネット配信の場合はそれが通用しない。
そして権利者は「ニーズが少ないものをサーバー上に置く」ということについて、僕が思っていた以上に興味がないようだ。
ミュージシャンが売ってくれといっても耳を貸さない。
ネット配信オンリーになったら、物理フォーマットの時代以上に音源を入手することが難しくなるかもしれない。
ネットのみで配信される楽曲が、サーバーから消えた場合、その曲はほんとうに、「新たな聴き手を得ることがない楽曲」になってしまう。まぁ、ファイルの所有者が聴いたことのない人に聴かせたらいいんだろうけど、その聴いた人が「いい曲だねえ、どうやったら手に入るの?」と訊いた時に「もうどこにも売ってないんだよ。」と。
「残念だねえ、また聴かせてあげるから、そうがっかりするなよ。」と。
で、CD-Rとかに焼いてあげるなどというのは、当然、違法かもと言うことなんですね、少なくとも権利者はそう主張し法律上「私的範囲での使用について複製を認める」ということなんで。これはDRMフリーかどうかというのは関係ない。
著作権は50年保護されている。70年になるかもしれない。
音楽出版社の倉庫に放置され、所有者も転々と変わり、70年後にパブリックドメインとして発掘されるであろう音楽ファイルが入ったハードディスク。スイッチを入れても動かないかもしれない。DVD-Rは読み取れないかもしれない。読み取れても再生するソフトがないかもしれない。
まったく、僕の考えは甘かった。
結局、コンテンツの死蔵を何らかの形で制限する法制度がないと解決しない問題なのかもしれません。
ユニバーサルの店舗は遠い
以前のユニバーサルの話の続き。
Universal Music、DRMなし楽曲の販売をテスト(ITmedia)
Universal Music to Start DRM-Free Experiments(DRM Watch)
Universal Music、DRMなし楽曲の販売をテスト、しかしiTSは仲間はずれ。(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
ITmediaから引用。
同社は8月21日から1月31日までDRMなしの楽曲を販売する。(中略)同社によると、DRMなし楽曲を販売するオンラインストアは、Amazon.com、Google、Wal-Mart Stores、Best Buy、Rhapsody、Transworld、Passalong Networks、Puretracksなど。
へぇ、、、僕は買えるんですかね。
れし氏のとこから引用。
そして、世界でのこのような動きに対して、日本は蚊帳の外(苦笑)
買えないのかよ。。。
18日、追記でリンク。英文記事。
Music Industry Accelerating Watermarking Adoption(DRM Watch)
マイクロソフト社のウォーターマークを採用してるらしい。
それでウィンドウズユーザーのみ対象なんですね。
記事に拠ると「どこから購入されたファイルか」ということだけ書き込まれるらしい。そんなこと透かしに入れてどうするのだろう。
全く、無駄としか思えない。
誰でも買えるようにすることの方が余程重要だろうに。
Jul 08, 2007
廃盤はなくならないのか
うーむ、、。
[WSJ] Universal Music、iTunes Storeとの関係に距離?(ITmedia)
ユニバーサル、iTunesの契約更新を拒否(Engadget Japanese)
いつまでたっても「廃盤」という概念は消えないのかもしれない(what's my scene? ver.7.0)
単純に、売れないからとか在庫多すぎとかで廃盤になるというんじゃないらしい。
企業が戦略・交渉の道具、弾としてコンテンツを扱うことで、ネット上で廃盤になるということが起きるということらしい。
いや、ちょっと言い過ぎか。
現状、むやみなベスト盤や企画編集盤の販売とか、コンテンツは企業の弾なわけで今更な話。
それは単純にネット販売に移行したからといって変わらないよ、ということか。
記事に拠ると、ユニバーサルはiTSでの販売に不満があるらしい。
以下、ITmedia記事から。
だからといってこの動きは、Universalが見通せる範囲での未来において、エミネム、50セント、スティングを含む自社の膨大な楽曲カタログをiTunes Storeから引き上げることを意味してはいない。市場占有率で世界最大のUniversalは、1年以上の長期ではなく、短期間の販売契約を結びたいと希望している。
個人的に思うのは、どこから販売されようと、DRMフリーでうちのiTunesとステレオ装置で再生できるなら、そこは文句は無いよってことがひとつ。ユニバーサル本社のサーバーからでも買いますよ。
しかし、あんまり安っぽいファイルを1枚300円とかで売られた日には怒る。
ネットショップのインターフェイスが分かりにくくてどこにいったら何が買えるのか分からないってのも困るな。
ウィルスめいたものが埋め込まれていたり専用のソフトが必要でおかしな挙動をするとかはNG、マックで聴けないとか問題外。
希望としては、とりあえず国境を無くしていただきたい。
iTSでは買えない曲が多すぎる。
ユニバーサル本社のサイトで売るなら日本語表示が出来るようにして欲しい。フランス語はわかんね。
いろんな店があるというのも、いいんじゃないかと思う部分があって。
しかし実際、廃盤になるというのであれば、とても残念。
記事では廃盤になると決まったわけじゃあないということだが、しかし、日本のiTSでは安全地帯の音源が半分になっっているという話があったり、どういうことだろうなあ。
SMEとかは、既にネット配信していた音源を廃盤にしている。
ミュージシャンが配信を求めた訴訟ではミュージシャンサイドが敗訴していたり。
売りたい人がいて、買いたい人がいるのに、権利者がどうとか言ってお蔵入りしてるのって、まったくおかしい話だと思う。
一応、裁判所にリンク。
THE BOOM音楽事務所対SME:
平成18(ワ)1769等 送信可能化権確認本訴請求事件 平成19年01月19日 東京地方裁判所(裁判所)
HEAT WAVE対SME:
平成18(ワ)8752等 送信可能化権確認本訴請求事件,反訴請求事件 平成19年04月27日 東京地方裁判所(裁判所)
Jul 01, 2007
クリップ
いくつか気になったエントリーや記事をクリップ。
アーティストから著作権を譲渡された団体が、アーティストの著作権を保護・拡大すべきだと主張する狡猾さ(P2Pとかその辺のお話)
しっかり書かれた論説。
あなたのケータイやブログは大丈夫か——ネット時代の著作権考 (1/2)(ITmedia)
「高音質配信」は本当に“いい音”か?——iTunes Plus編 (1/2)(ITmedia +D LifeStyle)
こっちはオーディオやってる者として気になる記事。
記事にある通り、コンポによっては音源によって如実に音質差が現れるということは、自分にも実感としてあります。
Feb 10, 2007
EMIの件(追記、アップルの件。どんな音源が欲しいのか)
メモ。
EMI、「全曲DRMなし」での販売を検討?(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
どうでもいい話:諸行無常(what's my scene? ver.7.0)
全てのCDをコピーコントロールにすると言った頃のEMIのThe CEO & chairmanが、Alain Levy氏だ。
昨年末にCDは死んだと言って、今年に入ってクビになったという話。
そんなEMIが今度はDRMなしだというのは、反動なのかもしれないが。つうか、CDってDRMないんだよね。
そういうのが結局、一番便利。
まず、リンク。
Steve Jobs の公開書簡(仮訳)(maclalalaweblog)
分かりやすい。
まったく、Steve Jobsのいうことはいちいちもっともで、当たり前すぎる。
そんな当たり前のことがなかなか通らない。
えーと、EMIがDRMなしの配信をするかもということだけど、気になるのはどんな配信になるのかということ。
まず、価格。
さすがにDRMなしでも高かったら、買う奴少ないだろう。
ある程度、価格は抑えられるのではと予測。
音質。
mp3ということなんで、期待しない。
思うのだけど、いっそ無圧縮で売ればいいのに。しかも96kHz/24bitとかで。
音がいいし、ファイルが大きいからコピーしずらいし(w。
製作現場の音からCDレベルまで落とす必要ないから楽でしょ、いや、制作現場ではもっと高音質なんだっけ?
mp3が150円、96kHz/24bitが300円なら、自分は96kHz/24bitを買う。
売り方。
それだけで正規音源として売られるケースもあるだろうけど、どうなんだろう、正規音源がmp3だけ?
そういうのに適さない音源も多いはず。
そもそも、ブルーノートがそうだった。
むしろ、CDで売り、mp3でも売り、というのが多いんじゃないだろうか。
mp3だけからの収益はたぶん少ない、おそらくCDも売った方が利益を見込める。
バージョン違いを売るとか。
CDで売られる奴の先行リリース、ショートバージョンとか何とかmix、そんなの。
ファンならどっちもゲットしたがるだろうということで。
、、、なんか、やだね。やっぱり高音質ファイルを売る方がいいよ。
CDで十分な人はCDを、より高音質を求める人はファイルを買う。
コピーされる?
だったら何か?
コピーできるCDは今でも売られている。
しかし、憶測なんだよね。
Jan 21, 2007
不可逆圧縮でいいのかい。
あちこちで語られてる話だけど。
オリジナルのCDをごみ箱に捨てる若者(bpspecial ITマネジメント)
CDを捨ててしまう若者、、、別にそれはいい。
案外自分は、淡々と受け止めている。
なんつうか、自分の場合、収納の為にケースを捨てはじめた時点で、けっこうそういうこだわりは抜けた気がする。
捨てる人がいてもいいやっていうか。
そういえば、iTSとかで買った場合付いてくるアートワークは、ああいった形にこだわる必要はないと思うし、歌詞とかのダウンロードとか、そういうのも込みで、もうちょっと熟れてもいいと思う。
そんなことよりも問題なのはこっちだ。
パソコンに圧縮して格納しておけば、またその音楽CDが欲しくなったらCD-Rに“焼直せば”復元できる。そういうと、「一度圧縮してしまったら、オリジナルの音質には戻らないよ」と思う方もいると思う。僕もそう思ったのだが、「圧縮した音楽とオリジナルの音楽の違いは、人間の耳には区別できないでしょ」というのが彼の考え方である。
何いうか。
その「彼」というのはミュージシャンだというが、「音色」というとこまで気を使うかどうかは各々のミュージシャンの勝手だろうけど、そういう人ばっかりだと思って欲しくないなあ。
音質に配慮してSACDとかでリリースする人だっているのだ。
SACD、捨てられないぞ。
現時点で、CDDAの方がファイルよりも音がいい以上、捨てるわけにはいかない。
つうか、可逆圧縮か、圧縮せずに取り込んで聴くなら、ハードウェア次第でCD並みの音質になるだろうけど、それなりのオーディオを使えば不可逆圧縮ってのはやっぱり音質は劣るのだ。
このコラム自体は、知的所有権の関係でなかなか興味深い話が書かれていて、とても面白く読ませていただきました。
追記なわけです。
このコラム、そもそもCDを捨てるって話よりも知的所有権の問題の方が主旨なわけで。
そっちのほうも少しだけあたっておこう。
オリジナルの音楽CDを捨てたりしないで、僕にくれればいいじゃない……。そんな風に思うのだが、「それは違法コピーと変わらないですよ」という返事になる。
誰かの手に渡ると、その分、その誰かが買うかもしれなかった本来の音楽CDが売れなくなるかもしれない。それではアーティストに迷惑がかかる。だから彼自身の手できちんと捨てることが彼にとっては大切なのである。
この彼の考え方は、知的所有権の考え方としてはきわめて正しい。
(中略)
しかし実は、世の中の“仕組み”としては大きな問題を抱えている。彼のパソコンに入っている音楽CDが、本当に彼自身が自分のお金を出して購入したものかどうかを証明する証拠が存在していないのだ。
なぜなら、彼が買ったというオリジナルであるところの音楽CDは、すべてゴミ箱に捨てられてしまったのだから、彼のパソコンに入っている音楽ファイルが元々、彼のものだったのか、例えばWinny(ウィニー)経由で不正に入手したものかを証明する手立てはない。
なるほど。
ちょっと考えて思い至ったのは、それなら「帯」を購入証明としてストックしとけばいい。
あれだけだったら、そんなに場所もとらないし。
でも輸入盤には帯がないな、、、レシートとっとく?
僕はケース以外は、ブックレット、歌詞カード、帯も保管している。
のだけど、それらを全部捨てるとなると、購入したという証明は確かになくなる。物そのものが「所有の証明」だったわけで。
でも、考えてみたら盗品でも区別は付かないよね。
誰かが車を乗り回してるのを見て、盗んで乗ってるよと思う人はいない。
そう思うのは、「あいつ車持ってなくて無免許のはずなのに運転してるよ、どうしたの?つうか、あの車誰のよ。」と思う誰かの友人なわけで。
疑心暗鬼はきりがない。
僕の目の前にある朝食の皿、これはどこかから盗んできた物じゃないと、誰が証明できる?
所有の証明が問題になるのは、やっぱりコピーが問題になるからだろう。
簡単にコピーできるというデジタルの諸刃の剣が、所有の証明なんていう、一般常識内の暗黙の了解で済んでたところに、不安定要素を持ち込んでしまった。
そこまでメクジラたてなくても、とも感じるけど、、。
えーと。
このコラムに出てくる「彼」は、所有するということについてどう思っているのだろう。
極端な話、彼は多分、脳内に音源があれば問題ないのだ。
ハードディスクは記憶の補完にすぎない。
音楽はともかく、読んだ本を捨ててしまう人もいる。古本屋に売るとか。
読んでアタマにはいってるから、手元には要らないんだそうだ。
忘れないのかアンタ、と僕のような忘れっぽい人間は言いたくなるが、実際、そいつに訊いたら、時間が経つと内容を忘れるそうだ。そりゃ大抵そうだ。
僕は、忘れたときに読み返すことが出来ないのがイヤなので、何年も前に読んだ本を捨てずに置いている。
まぁ、思い入れというのもあるけど、ふと思った時に引っ張りだして来れないという方がイヤなのだ。
実家に置いてある諸々の本、いつ捨てられるかというリスクはあるし、すぐに手元にはないけれど、取ってこようと思ったら取ってこれる、と思っている。
結局、これも脳内記憶の補完なのだ。
図書館なんてものが世の中にはあるが、これは社会的に知的財産の記憶を補完しましょうってことだ。
市民は市立図書館の本を「所有」してるのとおんなじだ、って言い方したら少し気分いいかも。
なかなか行けないけど。
今後は音楽CDについても、パソコンソフト同様にユーザー登録をする方向で考えていくのもいいのではないかと思ってしまう。
そして、ユビキタス環境で使う、と。
これって、=DRMをどうするかって話にも関連すると思う。
CDで行う音楽のユーザー登録は、SMEがレーベルゲートCDでしようとしたことだと思うし、次世代CCCDのrootkit騒動があったりで、なんだかもう、難しいんじゃないかという感じがする。よっぽどユーザーの理解が得られる形にしないと。
でもファイルに関して言えば、今後どうすればいいかという話が、まさに始まったばかり。
図書館の本にはラベルが貼ってあるけど、持っていこうと思えばどこででも読める(ただし公共物なので大事に、貸し出し期間中に返しましょう)。
プチ・ユビキタスって感じか。
そういえば、自分の本にハンコ押してる人がいるね。××蔵書とか凝ってるのもある。
もしかして音楽も、自分のファイルに自分のハンコが押せたらいいんじゃないかな。
JASRACだったか電子スカシの研究してたっけ。
応用効かすこともできそうな。
でも、そんなハンコ押したからって、自分に何の得があるのか、って思ったりもしますが、そのあたり、アップルのFairPlayがオープンになるという噂もありますが、そんなあたりと絡めたら落としどころが見えてこないだろうか。




